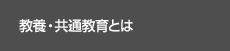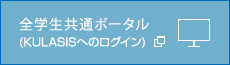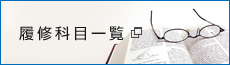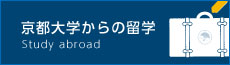芸術・言語文化系
芸術関係科目の分類
芸術関連科目では、主に西洋と東洋と日本の美術と音楽について、理解を深め、感性を磨くことを目指す。さらに、「美」とは何か、「芸術」とは何か、「創造性」とは何か、といった根本的なテーマについて受講生とともに考えていく科目構成になっている。
「基礎論」は、「芸術学」Ⅰ~Ⅳ、「創造行為総論(基礎篇)」と「創造行為総論(応用篇)」からなる。「芸術学」では、古代から現代までの具体的な芸術作品や美学思想を分かりやすく解説しながら、アートに親しんで感性を磨いていく内容になっている。「創造行為総論」では、芸術や美について著わされた優れた著作を取り上げ、偉大な美の思索家たちの思想に触れる。
「各論」は、「音楽芸術論Ⅰ・Ⅱ」、「東洋美術史Ⅰ・Ⅱ」、「近代芸術論B」、「創造ルネサンス論A・B」からなる。それぞれ順に、西洋の音楽の歴史、中国とインドの美術、日本の江戸・明治の芸術、西洋美術を対象とする授業である。
「基礎ゼミナール」の「創造ルネサンス論基礎ゼミナール」では、少人数のゼミ形式で、神話や宗教など、美術に取り上げられてきた主要なテーマに習熟することを目指す。
国語国文学関係科目の分類
国語国文学関係科目は、基礎的な内容を中心とする「基礎論」、より限定されたテーマを取り上げる「各論」、および少人数で講読・研究発表などを行う「基礎ゼミナール」で構成されている。
「基礎論」は、幅広く古典文学を取り上げる「国語国文学」Ⅰ~Ⅲと、同じく近代文学を取り上げる「日本文学」Ⅰ・Ⅱ、中国古典文学を取り上げる「漢文学」Ⅰ・Ⅱ、日本語を取り上げる「言学」Ⅰ~Ⅲがある。「国語国文学」「日本文学」は、『万葉集』『古事記』など文学の始まりから平安時代の和歌や物語、さらには明治・大正・昭和期の文学について、日本語学の知見とも関連させながら入門的講義を行っている。また、日本の文化と日本語に大きな影響を及ぼした中国古典文学をカバーする「漢文学」は、高等学校で用いられたなじみある教材を用いた入門的講義で、より深い理解を獲得することを目指している。「言学」は、日本古典文学の知見を踏まえた、日本語に関する入門的講義である。いずれも、理系学生にも配慮した内容となっている。
「各論」には、日本や中国の古典を読む「日本古典講読入門Ⅰ~Ⅳ」、「日本語学文献講読論Ⅰ・Ⅱ」、「日本古典講読論Ⅰ・Ⅱ」、「中国古典講読論A・B」などがあるが、中には専門性の高い授業もあるので、その内容・履修条件についてはシラバスで確認してもらいたい。
「基礎ゼミナール」は、少人数で講読や研究発表を行うゼミ形式の授業であり、受講者には主体的な授業参加が求められる。
言語関係科目の分類
言語関係科目は、言語を人間の思考とコミュニケーションの主要なツールと考え、思考とコミュニケーションのプロセスとメカニズムを解明し人間性の理解に迫ることを目標に、次のように体系化されている。
「言語科学I」および「言語科学II」では、入門的な内容ながら言語学の全分野(音論・形態論・統語論・意味論・語用論など)を網羅的に取り上げる。また、「言語文化論」は、ことばの諸問題、とりわけ異文化コミュニケーションに重点をおき、言語と文化の関係性について解説する。「実践応用言語学入門」は、言語学の成果を言語教育など実践的側面に活かすにはどのような分野があるのか、概観する。教職志願者などに向いている。これらに続くものとして、2回生以上向けの「言語構造論」・「言語機能論」・「言語認知論」・「言語比較論」が提供されている。いずれも、ことばに関する知的関心に沿った、わかりやすい授業内容であり、自身の興味に応じた中身かどうかシラバスで十分に確認してもらいたい。担当教員と事前に(あるいは初回の授業時に)相談してもらうのが望ましい。