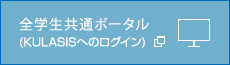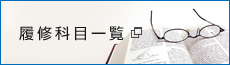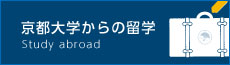環境の評価 2014年度

2012年に伐採された林分を視察し、環境と人間の関係を考えます。

緑色のネットの向こう(シカ排除区)と手前で草本の種類と量が全く違っている様子を観察して、動物と植物の保全についても考えます。

2009年に近代化産業遺産に指定されたトロッコに沿って、過去の人間活動を学びます。
【内 容】
このポケット・ゼミは、5月から7月にかけて教室で8回の討論形式の授業を行った後、8月に芦生研究林にて1泊2日の合宿を行い、自然と人間の関係に関わる森林環境を視察したあと、環境評価に関するレポートの発表と議論をするという構成で実施しています。環境の持つさまざまな価値を人間が認識し、自らの態度や行動を決定する際には、その環境の価値を判断している、という枠組み設定に基づいて議論を進めます。
○「環境を評価する」とはいったいどういうことか
教室でのゼミでは、人が事物を認識し「評価」することの意味の確認から、環境の評価が環境の価値判断となり、人の環境への態度・行動につながるという因果関係について議論します。環境を評価することの意味は、人によってかなり異なる意見を持っていて、理解することは簡単なことではありません。また、そもそも、環境に価値=「値段」をつけることに関して、真剣に議論することはほとんどないでしょう。このポケゼミでは、みんなと議論しながら、考えを構築していくことに意義があり、全学共通の少人数ゼミ形式であることは、大きなメリットだと思います。
○人間中心主義か非人間中心主義か
自分のものの考え方は人間中心主義的か、非人間中心主義的か、このポケゼミを受講するまで考えたこともほとんどないと思います。環境を評価する際の自分の観点を始めて認識し、他の学生の意見も聞くうちに自分の考えが変化する学生と変化しない学生がいますが、自問自答する姿勢は頼もしいものです。このポケゼミを受講して、自分か環境に対して、あるいは他者に対して、どのような関係性で物事を考えているか、じっくり考えてみませんか。
○記事に表れる「環境の評価」
レポートは、環境に関する新聞等の記事を自ら選び、そこに含まれる「環境評価」の文脈の抽出と解説が課題となっています。そのレポートの内容を芦生研究林の視察のあと、合宿形式(8月中旬、1泊2日の予定)で披露し議論することにしています。芦生研究林では、天然生林、人工林の観察に加え、林内数カ所で実施されているシカ排除実験地を観察したり、廃村の跡地を見ながら、過去の人間の森への関わりに思いを馳せます。
平成25年度の様子は、下記URLで紹介しています。
URL:http://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/blog/archives/12738![]()
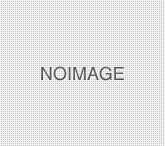
吉岡 崇仁
専門分野:生物地球化学
著 書:「森里海連環学」:2006/京都大学フィールド科学教育研究センター編/京都大学学術出版会、「環境意識調査法 -環境シナリオと人々の選好-」:2009/吉岡崇仁編著/勁草書房、「森と海をむすぶ川」:2012/フィールド科学教育研究センター編/京都大学学術出版会
自己紹介ホームページ:http://fserc.kyoto-u.ac.jp/wp/staff/yoshioka
http://www.forestinfo.kais.kyoto-u.ac.jp/yoshioka_JP.html