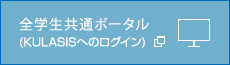インド哲学入門 2008年度
この前少人数セミナー(通称ポケゼミ)を担当したのは6年前のことである。そのとき受講した学生のうち二人がサンスクリット文学と仏教学に進学し、今年の3月に修士課程を終えた。他にも文学部だけでなく理学部や農学部、経済学部からも総勢10人が受けに来てくれた。そのときは「インドについて考える」というテーマで、私たちの身の回りに見られるインドのイメージを確かめてみて、いったい私たちはどんな風に日頃インドを見ているかということを反省的に考えてみようとしたのであった。インドへの理解のかたよりを別に笑おうというのではない。まずは自分たちの視線を反省してみようというのが、そのときのゼミの目論見であった。
さて今回は、ずばり「インド哲学入門」というテーマを立ててみた。いまだに「印哲」に惹かれて、数年にひとりぐらいは私の研究室に進学してくる学生もいるが、実際に入ってみると、最初のうちは語学ばかりで、やれサンスクリット語だ、やれヴェーダ語だ、英語は当然としてドイツ語もフランス語も必要だ、印欧語である以上ラテン語ぐらいは勉強しておけと、「印」の方はともあれ、「哲」の方がどこかに吹っ飛んでしまう。ようやくテキストが読めるようになった頃には、はや卒業ということになる。最近は、就職活動に時間を割くことも多いから、自分が選んだテキストを読むこと、すなわち卒論を書くことというようなことにもなる。それでも各自のテーマに応じてそれなりに立派な卒論を完成してしまうのはさすがであるが、果たして初めに関心があった「哲学」の方はどれほど深化したか。指導する私の方でも常に気になるところである。私が学生の頃もそうであったが、昔であれば、「印哲」などは、専攻した限りずっと研究を続けるのがあたりまえで、しかもそうそう職はなかったから、師匠から「この道を選んだ限りは、末期憐れと心得よ」と、のたれ死ぬ覚悟のほどを試されたものだが、おそらく今の学生にはなんのことかわからないであろう。こんな風に言ったせいで誰も進学して来なくなっても困るのだが、文系理系の区別や将来の専攻とは関わりなしに、インド的な思考法になじむことを目的にして、今回のゼミは進めたいと思っている。
「インド哲学入門」といっても、今回は、「インド人がゼロを発見/発明した」と言われることの意味を考えてみることにした。これはインド式算数がこのところはやっているからというわけではない。また、「ゼロ」というのは、仏教の「空(くう)」と同じ観念だなどとわかったようなわからない話をするつもりでもない。「ゼロ」という観念、「ない」という観念だけならば、そんなものはいつでも誰でももっていた。インド人が発見/発明したのは、「ゼロ」という観念を記号で表し、それを数として扱うということである。「ない」ものをかたちで表す。それにオペレーションの中での一定の機能を果たさせる。これがインド的思考法の得意技である。このことを、インド哲学や文法学、数学の原典などをいくつか使って、具体的に考えていくことにしたい。原典だから、もちろんサンスクリットで書かれているが、すぐれた翻訳もいくつかあるから、日本語と英語ができれば、まずは大丈夫である。ちなみに、「ゼロ」に関して、12世紀のテキストには、例えば次のようなことが言われている。
「世界の壊滅と創造のとき、どんなに多くの生類たちが[その体内に]入ったり出たりしても、無限にして不滅なるもの(ヴィシュヌ神)には何の変化もない。ちょうどそのようにゼロ分母なる量も、どんなに多く[の数]が入ったり出たりしても不変である。」(バースカラ『ビージャガニタ』20。林隆夫『インドの数学』、中公新書、1993年より。)
「ゼロ分母」とは、ゼロを分母としてもつ数のことで、つまりは「無限」のことだとして、バースカラはそれをひとつの数として扱っている。20世紀はじめの孤高のインド人天才数学者として世界にその名を知られているラマヌジャンは、「0は絶対実在を、無限(∞)はその多様な顕在化を、そして両者を掛け合わせた積、∞×0はあらゆる数を表徴し、そのひとつひとつが創造の営みに対応している」(ロバート・カニーゲル著『夭逝の数学者・ラマヌジャン 無限の天才』、工作舎、1994年、70頁)と言ったとされる。この言葉は、哲学者にも数学者にも理解されなかっただろうというのが、カニーゲル氏の評価だが、そんなことはない。インド哲学史や数学史の文脈におけば、後者は前者の変奏曲であり、長い時の流れを経て生き続けるインド的思惟のかたちであると言ってもよいのではないだろうか。今回は定員八名のクラスである。どんな学生が来るか楽しみである。

赤松 明彦(あかまつ あきひこ)
1953年生 京都出身
京大文学部卒 パリ大学博士課程修了
専門:インド哲学