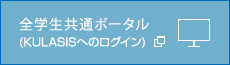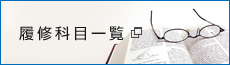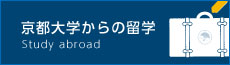第1回 初修外国語担当教員による座談会
今日は、ありがとうございます。教育院では、昨年の5月頃から、いろんなワーキング・グループで議論してきました。私は数学ですが、自然科学だけでなく、初修外国語や英語の集まりにも顔を出して、非常に面白い話が聞けました。そのときに思ったのは、これは我々が聞くだけではもったいない。学生、特に新入生が聞いたら役に立つのではないかということです。今日の座談会は、初修外国語の先生方にお集まりいただきました。ワーキング・グループの時とは違って、今日の話の相手は学生ということで宜しくお願いします。では、多賀先生からどうぞ。

私自身はフランス語を教えておりますが、今日は初修外国語部会の部会長という形で参加させて頂いています。初修外国語というのは、今現在の大学の状況の中で非常に難しい立場に置かれている。英語中心の世界になったおかげで、従来、ドイツ語にしろ、フランス語にしろ、あるいはもっと遡れば中国語にしろ、英語以外の外国語を学ぶということに関しては、日本にとっての一つのモデル、先例というような形でそれなりの意味があって、学生さんもそれを共有してくれていたのですけども、今そういった価値観の共有が学生さんとはもう出来ない状況になってきている。とりわけ英語中心で学問が進んでいる理系の学生さんにとっては、英語以外のもうひとつ別の言語を学ぶということの意義がほとんど感じられないという状況になっている。それプラス初修外国語を学ぶことの困難さというものもありますが、そのあたりのことを今日の座談会で、新しく入ってくる学生さんに、なぜ初修外国語、英語以外の外国語、言語を学ぶ事が必要なのかということ、それからもし選ぶとすれば、どういうような基準で選んでいったらいいのかという話をできればいいかなと思っております。こうしたことをやってみようということは、従来から入試が終わって京都大学に入学が決定した学生さんが、その後初修外国語をどれかの言語を選ぶまでの間の時間が非常に短くて、ほとんど何も内容のある情報がないまま選択をさせられていたという状況を、何とか変えたいということが去年ぐらいからずっと懸案だった訳です。この試みはごくわずかではありますけど、その第一歩かなと感じております。
という訳で、今日はそれぞれの言語を代表して、一名ずつ先生が参加してくださると思いますので、ご自身とその言語の関わりから始めて、その言語の魅力であるとか、勉強の仕方など色んなことを話して頂ければいいかなと思っております。以上です。
いきなり英語とそれ以外の言語についての、厳しい話がでてきました。
それでは、最初にまず、大学の研究者としての自己紹介、どの外国語の担当であるかということも含めて自己紹介をお願いします。

私、服部と申します初修外国語ではロシア語を担当しております。それで、まずなぜ私が学生時代ロシア語を選んだかというと、これは学生さんには参考になりませんが、へそ曲がりな性格でして、私がちょうど大学に入学したとき、もうずっと昔ですが、日本と中国が国交回復するという、日中国交回復、そしてパンダが上野動物園にやって来るという、今の若い学生さんには想像もつかないでしょうけども、何時間も並んで30秒くらいしかパンダを見られないという、そういう時代でしたから、今と全く同じ、今以上に中国語が大ブームだったんですね。それでへそ曲がりだったもんですから、ドイツ語やフランス語は最初からやる気がなかったので、中国語もすごいブームなんで、消去法でロシア語しか残らなかったということで、入学願書にロシア語というとこに印をつけてしまって、この道に踏み込んでしまったということが正直なところです。これが学生時代に選んだきっかけです。本当に何のことはないへそ曲がりな性格だけです。あまり今の学生さんの参考にはならないかもしれません。
一周しますか?
そうですね。では、今の話で回しましょうか。担当されている言語に興味を持ったきっかけということでお願いします。
 ドイツ語の奥田です。今服部先生の方から、どちらかというと消極的な理由だったというお話が出ましたが、私もどちらかというと、ドイツ語が非常に好きだったとかドイツ語しかないというような積極的な理由じゃなくて、どちらかと言うと消極的な理由でした。
ドイツ語の奥田です。今服部先生の方から、どちらかというと消極的な理由だったというお話が出ましたが、私もどちらかというと、ドイツ語が非常に好きだったとかドイツ語しかないというような積極的な理由じゃなくて、どちらかと言うと消極的な理由でした。
当時はドイツ語とフランス語が多かったんですけど、男女比でいうと、フランス語っていうのは女性が比較的多いんです。フランス語の先生方全体が、我々学生から見ると非常にエリートっぽい雰囲気を醸し出されているというか、それに対して、ドイツ語の先生方はどちらかというと、今の言葉でいうとオタク的というか地味にやってますよという感じで。そういうフランス語の華やかな雰囲気というのがあって、それだったらドイツ語かなっというふうな感じで、比較的消極的な理由ですよね。
もともと小説を読むのが好きで文学には興味があったんですけども、そっちの方から言っても、やっぱりロシア文学とか日本の小説とかの方が好きだったんですけども、関西の大学で当時ロシア文学が学べるっていう大学はほとんどなかったんじゃないかと思います。
人生というのはなかなか思っているようには進まないもんで、消極的な理由で選んだことが、その後にそれと関わっていくようになるということはよくあることで、そういう意味では外国語の選択もそういう形で私の場合は決まったという感じでした。天野先生お願いします。

イタリア語の天野です。イタリア語と私というのは、私はカンツォーネですね。イタリアンポップスと最近では言ってますけれども、こういう歌が好きだったというのがきっかけと言いますか、始まりです。
イタリア語を選択したのかというと、それはしてません。当時はイタリア語は選択できなかったんです。もう40年前になりますけれども、その頃私は工学部の学生でして、選択したのはドイツ語でした。ドイツ語はかっこいいなと選択したというのが率直なところですが、先ほど多賀先生がおっしゃってたように、現在、初修外国語というのは特に理科系の学生にとって意味がわからなくなってるというようなことをおっしゃってましたけども、これは40年前でもやはり同じでして、当時の工学部の雰囲気からしましても、英語以外の初修外国語はほとんどどうでもいいというのが、全体の雰囲気でした。先生方がそう思ってらっしゃったかどうかは知りません。ですけども、入ってくる学生なんかの気持ちとしては、そうでしたね。イタリア語はそういう訳で選択できませんでしたので、大学に隣接してます東一条のイタリア会館、こちらでイタリア語を勉強しました。その後、先程ドイツ語の奥田先生がおっしゃったように、人生どうなるかわからんということで、結局今文学部でイタリア文学の先生をしてまして、そういう訳で皆さんが入ってこられて初修外国語でイタリア語を選択なさっても、私が担当する授業というのは現在ありませんけども、コーディネータをさせて頂いてますので、テキスト、これもイタリア会館で作られたテキストですが、これの作成にも深くかかわっておりますし、何かと宜しくお願いしますというところです。
 アラビア語の岡です。私の場合は、東京外国語大学のアラビア語科に入学し、専攻としてアラビア語を学びました。私の中では高校の1年生ぐらいの時から、自分は東京外大に行くんだと心に決めていまして、今から何十年も前のことですが、当時はまだ「海外」とか「外国語」という言葉がきらきらと輝いていた時代でした。
アラビア語の岡です。私の場合は、東京外国語大学のアラビア語科に入学し、専攻としてアラビア語を学びました。私の中では高校の1年生ぐらいの時から、自分は東京外大に行くんだと心に決めていまして、今から何十年も前のことですが、当時はまだ「海外」とか「外国語」という言葉がきらきらと輝いていた時代でした。
今は本当に時代が変わったなと実感するのは、高校生の時に修学旅行で海外を経験していたり、子供の時から家族旅行で海外に行ったりという学生さんがたくさんいます。1回生の半数以上がパスポートを持っていたりします。でも、私が高校生だった頃は、「東京外国語大学」という名前が本当に輝いていて、では何語科に行こうかなという時に、他の大学で勉強できる言語ではつまらない、せっかく外大に行くんだったら外大でしか勉強できない言語がいいと思いました。そうすると、モンゴル語とかタガログ語とかウルドゥー語とか色々あるんですけど、タガログとかウルドゥーなんて聞いたことがないし、モンゴルと言ってもジンギスカンと草原のイメージしか思い浮かばなくて、唯一、具体的にイメージできたのがアラビア語でした。今思うと、非常にオリエンタリスティックなイメージなのですが。
もうひとつ、なぜか子どもの頃から、パレスチナゲリラによるハイジャックといった事件があるとすごく心に残っていたんです。当時はジャーナリスト志望ということもあり、それやこれやでアラビア語を選ぶことになりました。
多賀先生もお願いします。
私も一応言わせて頂きますと、消去法でもないんですが、とんでもなくいい加減な選び方ということになるかもしれないです。最初は私もドイツ語をやっておりました。京都大学に入りまして、何を言語として選ぼうかという時に、さしたる考えもなく一番難しそうなのをやっとけばいいだろうということでドイツ語を選んだんです。ところが私は一年生の時アメリカンフットボールに入りまして、そうしますと家に帰ったらまさに玄関でばたっと倒れて寝てしまうというその生活が続いて、かろうじて単位はいただいたんですが、1年間やってドイツ語の何を覚えたかなって、後で考えると先生に申し訳ないんですが、そんな状態でした。
二年生になって、なんぼなんでもこれでは、アメフトの人に申し訳ないけれども、京大に入った意味がないだろうということでアメフトは辞めたんですが、かと言ってドイツ語をもう一度最初からやるのも、なんとなくやりにくくて、それでフランス語を第二外国語として、第三外国語かな当時の言い方では、としてやり始めたんです。そうしますと、これが非常に親和性があるというか、自分との親近感と言いますか、やり易かった。ドイツ語では色んな面でストップがかかっていたのが、全部がさーっと流れていく。文法もなんでも全て簡単に覚えていけるというような、なぜかそのような相思相愛状態みたいな感じになりまして、興味のある作家とかもフランス系が多かったということで、その後フランス語を中心にやっていくということなりました。
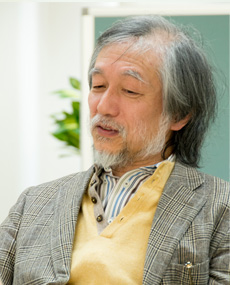
私の場合は、高3になった時に、「文系か理系かどっちかにしないとまずいんじゃないですか」と担任の数学の先生に言われて、ならば、ずっとおもしろいと思ってきた数学をやろうと決めたんです。
大学に入ってロシア語を選びました。その頃はスプートニクとかがあって、ロシア語のクラスが多かったです。ソ連の数学ということも少しは意識していたと思います。ところが、私の学年は2年目がストライキで、一年生の時に一生懸命ロシア語を、それこそ英語のつづりを書く時に、nとpを間違えて書くぐらいまで一生懸命やったんですけど、2年目はストで、1年間かけて覚えたことを次の1年間で完全に忘れてしまいました。とんでもない時代だったんです。