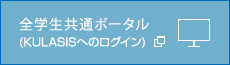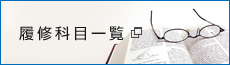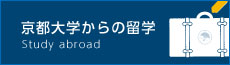第1回 初修外国語担当教員による座談会

ロシア語の服部ですが、天野先生がご指摘されたように、第二外国語、初修外国語を学ぶ価値があるのかっていう議論は今に始まったことでは実はない、本当に昔からあったし、少し前の教養部、それから平成10年でしたか、今から16年前、平成10年にやはり大きな座談会がありました。実際に学んでいる、法学部とか文学部の学生さんという、1回生・2回生の諸君に集まってもらってそれと先生方、ドイツ語の稲田先生とか、フランス語の東郷先生とか、それから英語の水光先生とか、教員と学生諸君が集まってこういう座談会があったんですよ。その頃から、なんで第二外国語がいるのという意見が学生さんから具体的にどんどん寄せられていて、その時も開口一番説明があったんだけど、さっきの多賀先生同様の堅い説明だなって、学生さんが聞いたら引いちゃうかなと、教員の意識を変える必要があるのかもしれません。第一にそれは思いました。
自分の専門の話に戻りますが、私は高校の時は文系理系で迷いまして、数学や化学は結構できたんですけど、物理が全然できなくて、それで理科はだめ、じゃあ文化系かというと、クラスメイトにものすごくそっち方面でできるのがいて、今、政府税調の会長をやっている。だから法学部とか行ったら、あんな奴とずっとこれから先、高校・大学、もう疲れるなと思って、やはり消去法で。
国語の先生とは相性があって国語の先生が、迷ったら万葉集をやりなさいよ、とおっしゃった。
国語の先生は私たちの高校の卒業生なんですが、今でいうオーバードクターで早稲田を出られて、万葉集の研究では今知らない人はいないという大変いい先生で、ちょうど母校の国語の先生に。30そこそこ、同じ高校の先輩でもあるし、15、6の高校生と母校の先輩の30歳のオーバードクターの文学青年が、寝食を共にして議論してた。ちょうど色々なことがあって、三島由紀夫が割腹自殺するのはあの頃なんで、本当に色んな事を議論してた。その先生が文学部行けって、それで将来は何となく万葉集でもやろうかなと思って大学に入ったんです。
ところが大学に入ってみたら、偶然のきっかけで消去法でへそ曲がりでロシア語を選んだんですが、実はロシア語って、ちょっとロシア語をかじった方は分かると思うんですが、普通のローマ字と違うアルファベットを使ってますよね?実はよく見るとギリシア語と似ていて、物理で使うローとか数学のパイとか、ギリシア文字とよく似てるんです。
今のロシア語の文字というのはギリシア語の文字から作られた自然発生的ないわば二番手のアルファベットなんです。本当はスラブ人の人たちに昔キリスト教を布教するために、西暦862年と言われていますが、9世紀の半ば、日本では平安時代ですが、ビザンチンのお坊さんが人為的にアルファベットを作ったんです、キリスト教を布教するために。これが非常にオリジナルなデザインで非常に優れたスラブの言葉、音とか言葉のスペルに適した非常に優れたアルファベットです。日本語のカタカナ・平仮名・漢字じゃないですが、そのスラブ語の文字を表すのに今使われてるロシア文字と別の体系があったんです。実はもう一つあったんです。そんなことを大学に入ってすぐロシア語の先生から聞いて、これはなかなかおもしろいな、万葉集もいいけれどこっちもいいんじゃないかな、これだったら競争相手もいないしというんですけど、万葉集の研究は奥が深いですよね?競争相手がたくさんいますし、僕なんかの才能じゃと思ったんですが、スラブ語の文字の研究だったらなんとかくっついていけるかなと思って、しかもその先生は大変人格が非常に優れていて、この先生にくっついていけば学問的にもやるところまでいけるかなという出会いがあって、今の専門、簡単にいえばロシア語の歴史なんですが、ロシア語の歴史の専門をずっと続けることができたと、何の気はなしに消去法で選んだロシア語、へそ曲がりに選んでしまったんだけど、結果としては非常に幸せだったかなと思います。
学生諸君も今迷っても、最初に色んな先生からお話があったように、きっかけは何でもいいんです。どんなきっかけでも選んでみると、後から振り返ってみると良かったかなってところもあるので、あまり迷わず直感で決めていいと思うんです。その二つ目の英語以外の外国語をどうして選ぶかということは、いずれまた次のサイクルでお話ししたいと思いますが、以上です。

私は20世紀ドイツのノーベル賞作家であるトーマス・マンっていう、日本でも翻訳も結構されてますし、有名な作家だと思うんですけども、トーマス・マンの文学が専門です。トーマス・マンという人はちょうどナチズムが台頭してきたときに脂の乗り切った作家で、同じような世代の多くのドイツ人と同じく一つの選択肢として亡命という選択肢の前に立たされる訳ですね。実際トーマス・マンは10年近くアメリカに亡命しますが、アメリカに住みつくことはなくて、戦後しばらくしてヨーロッパに帰ってきて数年して亡くなるんですけども、その当時の彼が書いたものを、エッセイなんかで読むと、当時世界に圧倒的な力を持ち出していたアメリカの物質大衆文化というものに、彼がヨーロッパの人間としてどういうふうに感じたかというようなことがよく分かるんです。亡命していった多くの人達がそういう体験をしながらもやっぱりアメリカの文化に馴染めない人が多いと。しかし飛躍するようですけども、英語は世界共通語として広まっていますし、経済的にはアメリカが圧倒的に強い、経済・軍事的には強い訳ですけども、文化的にはヨーロッパの近代文化に依存しているところがあって、今言った亡命時代にやってきた多くのヨーロッパの人たちが戦後のアメリカ文化を築いていった、という面が強くあります。
それこそアインシュタインもアメリカに、トーマス・マンなんかと一緒に亡命した一人ですし、音楽に詳しくない人はあまり知らないかもしれませんけど、ブルーノ・ワルターとかも亡命して、戦後のアメリカの音楽界を引っ張っていったという側面があります。今現在のアメリカ大衆文化の代表とされる映画なんかとってみても、映画の初期のころは、ドイツ映画というのは世界的にシェアを占めていて、その中のマレーネ・ディートリッヒという女優は後にヒトラーに抵抗してアメリカに移っていた亡命者の一人で、戦後のハリウッドを支える一人になっていきました。現代まで続いてきている世界システムとしての近代というのを作っていったのは18世紀から19世紀のヨーロッパです。しかし今お話ししたように、19世紀とか200年前のことだけじゃなくて、つい数十年までそういう形で、アメリカの大衆文化にもヨーロッパの文化が影響していた。
今僕たちはアメリカの、パクス・アメリカーナなんて言われる世界支配の中で、ある種生き残りをかけた自分たちの生き方の選択を迫られてるわけですけども、そういうものの一つの例として、私が研究してます、トーマス・マンっていう作家の生き方なんかも大いに参考になるんじゃないかと個人的には思ってます。
やはりドイツ文学というのは深刻な雰囲気ですね、人生にとって非常に大変大きな問題と結びついているわけですが、私はどちらかと言いますとエンターテインメントが好きでして、イタリア文学でもダンテみたいな深刻なやつもあるんですが、あのダンテというのも実はエンターテインメント性というのは非常に強いものです。
ところで、どの国、あるいはどの言語、文学であっても、やっぱり時代による波があります。
いつの時代のものが一番面白いかと、これはうるさいことを言い出すとそういうふうに考える人間、読む側の価値観というのが反映されてきますので、そう簡単に言えることじゃないんですが、一般的に言いますと、イタリアの場合には14世紀と16世紀に重要な作品が産み出されてます。14世紀というのはダンテ、ペトラルカ、ボッカチオという3人が非常に有名で、それに次いで16世紀、ルネッサンスと言われる時代ですけども、これまた非常に文学が盛んだった時代でして、私の専門は16世紀なんですけれども、そういう事情ですので、イタリア文学をやるとしますと14世紀あるいは16世紀に落ち着いてくるというのが割と自然です。この16世紀の特に詩が私の専門です。ちなみに、後程言語の特徴というところからもお話しすることになるのかと思いますけども、イタリア文学というのは、どちらかと言うと小説のような散文よりも詩が中心になっております。
私が専門にしておりますのは、ルドヴィーコ・アリオスト、西洋では非常に名の知られた詩人でして、騎士物語詩というジャンルを代表する詩人です。騎士物語と言いますと、例えばこれはスペインの人ですけど、セルバンテスの『ドンキホーテ』が有名でして、これは騎士物語を読みすぎて頭がおかしくなって、というような設定になっております。
騎士物語というのはそういうわけで、必ずしも高い評価はされていないという風に思われるかもしれませんが、実際にはそんなことはない。私に言わせますと、スペイン文学の先生には叱られますけれども、セルバンテスなんかよりもずっとこちらの方がおもしろいと。ドンキホーテが読みすぎて頭がおかしくなったのもむべなるかなという感じがいたします。
私の専門は、現代アラブ文学とパレスチナ問題です。その二つは別々のものとしてあるのではなくて、私の中では一つのものとしてあります。
大学に入った時はアラビア語を身につけて、中東を駆け回るジャーナリストを将来の自己イメージとして持っていました。ところが大学に入って間もなくガッサーン・カナファーニーというパレスチナ難民出身の作家の作品を読みまして、ヨーロッパにおけるユダヤ人の悲劇はよく知っていたのに、そのホロコーストの犠牲者であるユダヤ人がパレスチナに国をつくった結果として、もともとそこに住んでた人たちが祖国を失い、故郷を追われて難民になってしまったということは、まったく知らなかったということに気づかされました。
それまでは、アラブ人というのは、これだけ歴史的に迫害されてきたユダヤ人がようやく持った国を攻撃して潰そうとする悪い奴らだと、完全にオリエンタリズム的な発想でホロコーストやイスラエルを考えていたので、カナファーニー文学との出会いを通じて、パレスチナとは何かということと衝撃的に出会うことになりました。そこから、中東の側から、ヨーロッパにおけるユダヤ人に対する迫害の経験も含めた、ホロコーストのアフターマスとしてのパレスチナ問題という視点で、それを文学を通して研究したいと思い、思想としてのパレスチナについて研究しています。ホロコーストというジェノサイドが20世紀にあって、現代世界を生きる私たちは、ホロコーストという出来事があったという事を抜きにしてもはや人間として現代世界を生きるということの意味を考えることはできない、ホロコーストとはそういう思想的な問題としてある。
同じように、パレスチナ問題に関しても、現代世界を生きる私たちの普遍的な思想的課題として文学を通して考えるという研究をしています。
私は今現在、専門的にやっていますのはフランスの現代思想になります。もともとはフランスの19世紀の詩、とりわけ難解とされるマラルメという詩人から始めたのですけれども、博士課程に入って20代後半の5年余りをフランスに留学することになるんですけれども、現代思想に移行するきっかけとなったのも、その間にフランスで直接授業を受けたり聞いたりした何人かの哲学者の影響です。
代表的な人はミシェル・フーコーという人ですけれども、彼が死ぬ最後の年の授業にかろうじて私は受けることができまして、非常に大きな感銘を受けました。それからジル・ドゥルーズという哲学者も大きな感銘を与えたのですが、哲学者というのは言葉で聴衆とか学生に語りかけて、それが日本でいうような存在であるとかというような哲学用語ではなくて、恐らくドイツ語でもそうなんだろうと思いますけど、ヨーロッパの言語で哲学をする場合は、日常語と同じ言葉が哲学的に定義されて使われてくる訳なんですが、日常の言葉を使いながら現代社会の様々な問題を扱って、それぞれの個性いっぱいに語りかけてきた彼らの魅力を肌で感じて、それで今まで現代思想をやることになりました。
学生さんには、京都大学へ海外から誰か偉い学者さんとか、理系でもそうなんですが、講演会なんかあれば必ず積極的に、訳がわからなくても出とけと言っています。そこで自分の人生が変わることはありますので。
目の前に哲学者なり偉大な科学者なりがいるというその存在感はネットではなかなか感じられないものなので、それはぜひ言っておきたいですね。