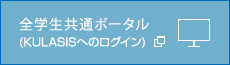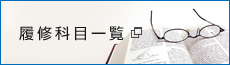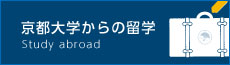第1回 初修外国語担当教員による座談会
奥田先生どうですか?

今の話の続きみたいになるんですけども、確かに英語一辺倒の今の現代社会の中で多極的な世界が存在して、いろんな文化があるんですよというのを、本当にその言語をある程度習得した上でそういうことを何がしか理解していくというのは非常に大変なことだと思うんです。
しかし、地名とか名前というのがその言語の読み方で読めること、これはそれこそその言語を多少とも勉強したらある程度すぐ読めるようになると思うんです。
例えば日本がそうなんですけども、現地主義というかその当の地名なり人の出身のその言語で日本語では表記するというのは、ここ10年、20年でも変わってきていて、かつては英語なり日本語に引き付けて発音していたものが今は割と現地の言葉で言うようになってます。例えば朝鮮半島の、今のキム・ジョンイルとかキム・ジョンウンとか、僕らが学生のときは金正日と言ってたと思うんですけど、それを朝鮮語の発音で読むようになってきていると。
同じようなことはドイツ語圏でも言えまして、今ドイツの大きな観光目玉になっているミュンヘン郊外の大きな城があって、ディズニーランドの城もあれをモデルにしたとか言われてますけども、そのお城をつくった有名な王様で、ワーグナーのパトロンとしても有名なルートヴィヒ王2世を主人公にして20年程前にヴィスコンティ監督が映画を作ったんですね、その時の日本での表記はルードウィヒと英語読みしてたんです。去年、ちょうどワーグナーの生誕200年ということがあって、またドイツでルートヴィヒ2世という映画がつくられたんですけども、その際はルートヴィヒというドイツ語式の読み方で書かれてたんです。
そういう風な名前ということに限ってみたら、日本では一般にも割と世界の各地のいろんな文化や言語があるんだというのを、ある種忠実に再現してきてるようになってると思います。そこでさらに大学でその言語について勉強するなら、名前がその人の現地の出身地の言葉で言えて、プラスそれぞれにニュアンスなり意味がありますから、そういうふうなものまで何がしでも感じ取れるようになるというのは、それほどその言語をきちんとマスターしなくてもある程度はできることだと思うんです。そういうふうな形で、その言語を大学で勉強したから、そういう一つのきっかけになる訳で、そこに大学で英語以外の言語をやる意味の大きな一つがあるんじゃないかと思います。
もう一つは最初の頃に、岡先生が言われてましたけど、20年なり、30年なり前の我々自身の大学生活の大学に入った時のことを思いだしてみますと、やっぱり英語以外の第二外国語、初修外国語というのはそれこそきらきら輝いていたというか、今まで知らなかった世界に触れられるという、きらきら輝いているものがあったんです。ただそういう輝きが確かに今は簡単に海外旅行にも行くし、大学に入ってくるまでに家族で現地に住んでいたとかいう学生さんも結構多いので失われつつあるのが現状です。
とはいっても、まとまって英語以外の言語を勉強するということは、これは理系・文系に問わず高校までにはなかったことで、大学生たる者の一つのアイデンティティというか通過儀礼というか、大学生って今までとどこが違うの?英語はずっと中高からやってますよと。なるほど、それぞれ専門にする学問は大学で深めていくわけですけども、理系・文系問わず大学から新たに学ぶことが始まりますよっていう、大学以前と大学以降を大きく分けるものの大きな一つが、やっぱり初修外国語なんです。そういう意味では大学生の一つのアイデンティティをつくる要素として、大学で英語以外のもう一つ言語を勉強するんだよと。これはさっき天野先生が何十年も前から理系の学生さんにとっては、初修外国語というのは、ある意味でどうでもいいような感じを持ってたということを言われてましたけども、多少僕は違ったイメージを持ってまして、確かに単位を取るのは大変で、そういう意味ではある種やっかいものというか、大変な科目だなという、なぜ勉強せなあかんねんという意識は持っている一方で、やっぱり理系の学生さんも多かれ少なかれ、大学に入ってきたんで今までと違うものが、こんなことを大学では勉強をするのかという素朴に一番わかり易い形で示していたのが、初修外国語じゃないかなという気がします。
ヨーロッパ言語に共通だと思いますが、それこそドイツ語でも、高校生以前と大学生というのは、同じ学生でも、シューラーとシュトゥデントと呼び方も全然違うわけです。大きく学校という一括りでは一緒になりますけども、高校までと大学とは違うんだと、実際色々と違うことがあるわけですけど、内容的に実際に違うことであって、しかも理系・文系問わずにある意味で共有できるものっていうのはそう多くはないんじゃないかなという気がします。その中で初修外国語を大学でやるというのは意味があると思うんです。
今奥田先生がちょうど名前の話をされたんですけども、個人的に名前をその人の国の発音で正しく読んであげる、名前を間違わずに呼んであげること自体が最初のコンタクトの始まりであったりもします。もう一つ僕が思うのは、ヨーロッパ系の場合は特にキリスト教系だと、聖人であるとか使徒の名前が大抵ついていて、例えばサイモンにしてもドイツ語ではジーモン、フランス語ではシモンであったりと、サイモンばっかりじゃないと。それからロバートばっかりじゃなくてフランス語だったらロベール、イタリア語ならロベルトとか、たいそうな言い方をすると、多様性の中で共通性があるんだよということです。
ヨーロッパ文化というのはそれぞれ別々の大きな広がりを持ってるけども、共通の部分があるんだよということも、名前一つとってもわかるんです。同じ名前がそれぞれの国の呼び方で発音で、フランス語でロベールというと何となく柔らかくて紳士みたいな感じで、英語のロバートというのと全然違うんですよ、イメージが。そういうようなことも含めて多様性と共通性というようなことが、英語以外にも一つやると肌で感じられて面白いかなということはありますよね。
あとアメリカ人の場合は、多くおじいさんの場合はイタリア人だったとか、その人の名前だけでもデ・ニーロとかね、顔を見てもわかるかもしれないけども、もともとこっち系の人かなという感じがしますしね、すみません。

ただね、私が思いますのは、初修外国語をやる意味っていうのは世代によってずいぶん変わってきていると思うんですけども、かつての意味と現在、そしてこれからの意味は若干違ってくるだろうと。現在すでにどうなっているかって言いますと、やはり実用言語としてはつまりツールとしての外国語というのは英語に集中してるだろうと思うんです。実際にはかなり以前からそうなってきている。初修外国語で英語以外の言語をやるっていうことは、二か国語以上とかあるいは英語以外に何かをということとは別に、要するに実用言語としてではなく外国語を勉強するという意味が非常に大きいんじゃないかと私自身は考えています。
どういうことかと言いますと、英語っていうのは高校、あるいは中学からずっとあくまでもツールとして勉強してきているわけで、これは翻訳可能だっていうことなんですよね。つまり、日本語で言えるようなことは英語でも言えるようにしましょうと、そういう意味でのツールです。ですけども、言語というのは実際にはそういうものじゃないんで、翻訳可能な部分というのは実は非常に限られているわけでして、岡先生が以前何かの機会におっしゃってたのが、コーヒーというアラビア語が日本におけるコーヒーの意味とアラブ世界における…ええ、私、コーヒーのことなんとおっしゃってたか忘れちゃいましたけれども…
カフアです。
カフアですか。そのカフアが持ってる意味とは全然違うんだと。要するにコーヒーというものが持っているそれぞれの社会における意味というのが全然違うから、これをコーヒーと翻訳してもあまり意味がないとおっしゃっていた。これは外国語を専門にしてる者にとっては当たり前のことなんですが、どうかすると忘れられやすいことなんです。
コーヒーなんて、見て触って飲むことができる、非常に具体的なものなわけです。それがそういう風に翻訳不可能だということになれば、ましてや抽象概念であります、自由とか、友情とか、宗教だとか、こんなものが翻訳できるのかって言ったら、全部できないものばかりです。それぞれの言語において抽象概念が出てきたら、それはすべて翻訳不可能だと思った方がいい。そういうことを実感するためには、ツールとしての外国語じゃなくて、一つの文化としての外国語というのを習得する必要があります。完全に習得するというのは多くの先生がおっしゃっているように、それは1年や2年でできることじゃないです。ですが、そういう世界があるんだっていうことは、確実に感じ取れるはずです。
私はそれが英語であってもおかしくないと思うんですが、英語の場合、我々は子供の時からツールとしての外国語としての勉強をさせられてきてますんで、今からそういう文化としての外国語として勉強し直すというのはかなり難しい。
こうした意味からも、英語以外の初修外国語を一つ勉強するというのは、かつては必ずしもそうじゃなかったかと思いますが、これからは非常に大きな意味を持つというふうに私は考えています。