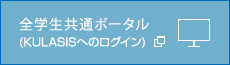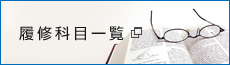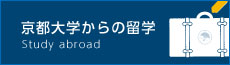第1回 初修外国語担当教員による座談会
さてそろそろ時間ですが、最後にお一人ずつ、学生に言っておきたいことをお願いします。
はい。ただ今の話、それぞれの語学の教育の伝統というのもあるだろうと思います。
私が先程申しましたようにイタリア語をイタリア会館に習いに行きました、その同じ頃、ゲーテ・インスティトゥートにドイツ語も習いに行きました。ですが雰囲気の違いは歴然でして、ドイツ語の方はずらっと並んでる受講生が先生の号令一下、前から順に大きな声でアインス!ツヴァイ!ドライ!フィーア!フュンフ!…、いや、かなりビビりました。イタリア語にはそういう雰囲気はございません。1回生向けには2種類のクラスがありまして、一つは簡略化した文法でもって、これは皆さんのまだ知らない用語になりますが、接続法、条件法といったものは除外して、動詞の活用というのはごく一般的な活用だけというふうに、割り切ってやるようにしております。専門家の中には、これで果たしてイタリア語をやったと言えるのかという疑問を抱く人がいてもおかしくありませんが、ここは割り切ってそのようにしております。
なるほど。そしたら、アラビア語はどんな感じでしょう?
私一人しかいませんので、初級の後期になるとネイティブの先生が実習に来て下さるんですけれども、イタリア語のようにモチベーションによってクラス分けとかできれば一番いんですが、それができないので、しかも他のヨーロッパ系の言語とかあるいは中国語、朝鮮語と比べて、テキスト、自習できるような色んなテキストが充実しているわけではないので、そうすると私の感じとしては、50人、60人の学生をしょって山を登って、皆をこの水準までもってこないといけない、なんだかすごくしんどいんですが、基本、先程申し上げたように、文法事項を分かってないと辞書が引けない。だから最低限辞書が引けるようになるための基本的な文法事項は全部やると。
2年目もとったら自分で辞書を引きながら、かなり苦労をしながらではあるけれども現代文が読めるようになると。これは2年でアラビア語が読めるようになるって実はすごいことですよね。もっと言えば1年でそこに書いてあるアラビア語が読めるっていうのは、それもすごいことで、特にアラビア語の場合、独学は非常に難しいと思いますので、そういう意味ではすごくお得かなと思うんですが。
もう一つ、先程は初修外国語を学ぶことの意味という形で一般論として申し上げたのですが、その中でも特にアラビア語を学ぶことの意味があるとすれば、アラビア語って文明の言語なんですよね。
中国語っていうのはある中国という一つの国の言語のみならず、中華文明の文明言語であるという意味では、アラビア語というのは、アラブ・イスラム文明の言語なんです。そういう意味での西洋文明の言語っていうと、なんなんでしょう?
古典ラテン語とか。ある時期まではヨーロッパの共通語ですから。
先程アラビア語でいうパンのイメージについて、実物のパンがどういうことだっていう話だったと思うんですけども、言語というのは、たとえ初級文法でやっている簡単なレベルでも、それぞれその瞬間に本物なんです。実物を体験できるんです。
ところが旅行ガイドブックであれ、大学の授業であれ、フランス文化論とかフランスってこんなところなんですよっていう話を日本語で聞くとかというのは、単にパンと言うイメージでパンと言う言葉だけ知ってるって、先程岡さんが言われたそのレベルなんです。ところが、
「情報」に過ぎないんですよね。

ですね。本当にひとつの単語でもいいし、ちょっとだけの文法でもいいですから、その言語に取り組むということは、その実物に手を触れているということなんです。それによってその文化のことが何かしら直接的に伝わってくる部分が必ずあると言えると思います。
最後に、どの言語を選べばいいのかというような基準みたいなものがもしあれば、自分のところの宣伝ではなくてちょっと言ってもらったらいいかと思うんですけど。冗談めかして言えば、例えば簡単な文章をドイツ語で読んで、今日は雨が降ってますっていうのをドイツ語で行ってみたり、フランス語で言ってみたり、イタリア語で言ってみたり自分で言ってみて、この言葉の響きは自分に合っているなというぐらい、ぱっと決めてもいいし、昔だったらそれこそ、大抵一番輝いていた時代には映画があって、ドイツ映画のあの俳優が好きとかあの映画が好きとか、イタリアのあれがいいとかいう何か自分の好きな感性の人がいる言語というのを、そういう好き嫌い基準、合う合わない基準で決めるというのもいいかと思いますけど。
多賀先生がおっしゃるように直感、京都大学に合格して喜ぶその時に湧いてきた心の中の自分の、魂の叫び、直感に従って選んでいいと思うんです。それで間違いないですよ。
とにかく西洋化した日本に何か疑問を抱いてる人はアラビア語をやったらいいと思う。
違いますね。ロシア人の根柢の中では、自分たちがアジアとか、騎馬遊牧民のスキタイ人とか、むしろ誇りを持ってるところもあるかもしれませんが、構文、文のつくり方とか日本語の構文と似たところもあるし、英語やフランス語やドイツ語には必ず文に主語が必須ですよね?どんなときでも。むりやりitとか必ず主語を使ってますよね。ロシア語とか日本語は主語が必須じゃありませんので。
そういう意味でも冠詞、定冠詞・不定冠詞もないし、いいかもしれませんけど。どれ選んだってそんなはずれはないから。どれも当たりくじ、どれも大吉だと思って引けばいいんですよ。
最後に補足しておきますけど、あまり当たりはずれで言ったらあれなんですけど、京都大学に入学するような若い人、京大生ぐらいの知的レベルを持った人が選んでさぼらずきちんと勉強すれば、これは立派なところまで行けますので、さっきツールとして英語は大事だという話が出ましたが、英語以外に何ができますかって言ったときに、若い京大生が一生懸命勉強するから必ずそれは英語と並ぶような立派なツールになる。
選んだら一生懸命それをやれば必ず自分のためになるし、身になるので、本当に安心して選んでほしいと思います。
そうですね。クラシック音楽の世界というとドイツ人が活躍してますんで、クラシックなんか好きだという人だったらおすすめだし、同じような意味でサッカーもドイツ。それこそドイツでは国技みたいなものですから。世界的にどのランクにいくかうんぬんじゃなくて、今のドイツ社会の中でサッカーというのはゆるぎない地位を占めています。
日本の野球みたいなところがあって、日本の阪神タイガースとミュンヘンのFCバイエルンってすごい共通点がありますけど。サッカーに興味がある人だったらそれなりに面白いことが見つけられると思います。
それから、最初にも言ったんですけども、それこそ自分はどちらかと言うとコミュニケーションが苦手だとか会話が下手だという人が、寧ろドイツ語は合ってるんじゃないかという気がします。
言語というのはコミュニケーションの手段であり、コミュニケーションと切っても切り離せないものなんだけども、寧ろコミュニケーションは自分は苦手だけれども、言語の世界を通じてその文化なりある種体系的に言語という形でまとまっているものに多少なりとも近づきたいという人に向いているんではないかと。これは自分が教えた実感というか、かなり独断と偏見ですけど。
その国の文化が好きだという人は多分迷ったりしないと思いますので助言は不要だと思いますが、迷った場合に絶対やめた方がいいのは、この言語が単位がとりやすい、この方が簡単そうだという、そういう基準で選ぶのだけはやめた方がいいです。
というのは、絶対的な意味で簡単な言語とか難しい言語とかはないからです。自分に合う合わないという点が、先程からいろんな先生がおっしゃっているように、簡単かどうかも決めてしまうわけで、純粋に客観的な意味で簡単な言語なんてないですし、難しい言語もないと思います。だからそういう選び方だけはしない方がいいと思います。
先程服部先生が「当たり」という表現をされたので思い出したのですが、1回生の学生が新入生へのメッセージとして、アラビア語をぜひとるようにと書いていて。その理由は、他の言語はクラス指定があり、先生によって厳しい先生、優しい先生がいて当たりはずれ、不公平感があるけれども、アラビア語は教員が1人しかいないから当たりはずれがないと。それは冗談としても、先程多賀先生がドイツ語は合わなかったけど、フランス語をとったら合ったというお話をされましたが、相性が良かったわけですよね。
でも相性の良し悪しって実際にやってみないことには分からないですよね。実際に言語を選ぶ時ってその相性も分からずに選ぶわけだから、これは服部先生がおっしゃったように直感で選ぶしかない。
アラビア語はアラブ世界で何が起こっても起こらなくても、毎年、50名内外の人たちが必ずとっている、つまり他の言語のように、日本との関係がどうこうなったから急激に増えるとか減るとかいうのがないんです。これは常に一定数、ある種へそ曲がりの人たちがいてアラビア語をとってるってことなのかなと思います。
それからもう一つ。初修外国語だけではないんですけども、京都大学全体としては、各先生の個性を非常に重要視するというのは勿論ずっと続けていくんだけども、今後全体の講義の中で各言語ごとの難易度の差をなくしていくようにしていきます。それぞれの特性はありますけれども。
それから先生ごとによって、あまりにも単位のとりやすい、とりにくいというのもなるべく少なくしていきましょうという方向で、授業の改革は進めているので、先程天野先生が言われた二重の意味で単位をとりやすいということはありません。その辺は逆に安心して自分の直感なりに従って、あるいは大志を持ってということで選ぶというのもいいんだけど、しっかり選択して頂ければいいかと思います。また堅くまとめてしまいましたが。
どうもありがとうございました。