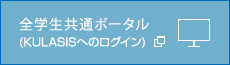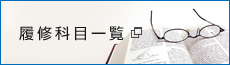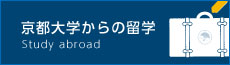第1回 初修外国語担当教員による座談会
今まで先生方ご自身のことをお話し頂いたわけですが、これからは学生の側に立って、新入生が選択するそれぞれの言語の特徴とか魅力についてお話し頂けたらと思います。
私、服部に戻りますが、ロシア語の場合には、まず文字がアルファベットが普通のローマ字と違うというところが皆さんに大きな印象を与えるかもしれませんが、まず大きなことは、文法的に覚えることが、最初、初級を始めるところですごく多いというのは、実は不利な情報なので最初はふせておかないといけないんですが、逆に言いますと、よく言われるんですが、最初に急な坂を上ってしまうと後は全く平らで崖を登りきってしまうと後は真っ平でということで、最初に覚えることは多いんだけども、ある所までいってしまうと、トルストイもドストエフスキーも読めるんです。文法の力って言うけど、割と覚えることは決まっているんです。
英語の場合は、今の場合は中学校から始めるわけでしょうけど、だらだら先が見えないというか、最初緩やかな坂なんだけども、坂の一番頂上がわからないですよね。いつまでたっても目の前に磨りガラスがあるような気がして、どうもわからない。特に構文と言いますかね、文の組み立てが、係り受けとかわからないですが、ロシア語の場合には最初に覚えることは多いんですが、そこを突破してしまうと後は平坦、ロシアの大平原じゃないですけど、真っ平ですので最初だけ努力がいる。
具体的に申し上げますと、例えば会話をしていて、話し手がいますよね?それから聞き手がいます。その他というか話す人と聞く人とその他という3つのカテゴリー、グループ分けができます。それぞれ単数形と複数形がありますから、3×2で、一つの動詞、例えば現在形とか未来形を覚える場合、動詞について6個の形を暗記しなければいけない。英語だったらずいぶん違う。英語だったら三人称単数現在にsがつくくらいですが、ロシア語では6個、全部覚える必要がある。過去形になると、今度、変化の基準ががらっと変わりまして、主語の、さっきは話す人・聞く人ですが、今度は主語が男か女か中性かって。複数形になると一緒くたです。単数男・単数女性・単数中性形、そして複数形という4つのグループ分けになりますが、変化の基準が性別に変わるわけです。そういう意味で動詞の変化形も、複雑です。それから名詞や形容詞の場合は、いわゆる格変化という、日本語の、昔風に言うと、てにをはですが、太郎がとか、太郎のとか、太郎にとかいう場合、ドイツ語をちょっとかじった人は4つありましたよね?1格・2格・3格・4格という、4つの格がドイツ語にはありますが、ロシア語の場合にはさらに多く、6個覚えなくちゃいけないということで、最初ちょっとびっくりするかもしれません。
実は古く遡って行けば、古典のギリシア語もそうですし、ラテン語もそうですが、英語でも何千年か遡れば似たような変化をしていたので、ロシア語は老舗の暖簾をいまだに守ってるというようなところがあって、ラテン語と同じように格変化が多いし、動詞の変化も多いですが、そこさえ、覚えるところは限られていますので、突破してしまえば後は非常に楽であると。その先は他のヨーロッパの言葉と特に変わらないので、関係代名詞とか様々な分詞、現在分詞、過去分詞というところを覚えれば、2年間きちんと勉強すれば簡単な雑誌の記事とか新聞のコラムなら辞書を引きながら読めるようにはなる、京大生だったら。1年間でも、週に2回の授業に行っただけでも簡単なメールのやり取りだったら読めるようには、京大生だったらちゃんとなりますので、特別難しいことはないです。
私たちが学生の頃は、普通の、外語大ではなく普通の大学ですが、ロシア語だけは他のドイツ語とかと比べて、ドイツ語とかは週に2コマだったんですが、ロシア語だけは第1学期は週3コマか4コマだったんです。カリキュラムが工夫されて、もし京大にもできたらもっといいんですが、仮に2コマであっても、十分京大生だったら使える、自分なりに納得できるところまでいけるはずです。
最初はちょっととっつきにくいかもしれません。後は特別フランス語とかドイツ語に比べて難しいことはないし、寧ろ発音は簡単かもしれません。あと、冠詞、フランス語とかドイツ語で難しい定冠詞、不定冠詞、冠詞類が一切ないので、寧ろ日本語と同じような発想でスッと入っていけるようなところはあります。特徴としてはそのくらい。後は文学の話とかそれはしだしたらきりがないので、後は色んなアニメのキャラクターとか最近流行っているのもありますから、特にそれはいいと思います。じゃ、ドイツ語で。
発音に関しては基本的にローマ字的に発音するんで、英語のように不規則性がないというか、発音という点では寧ろ英語よりも簡単な印象を受けるかもしれません。英語の次に学ぶ言語としては、中国語の場合は漢字という日本語と同じ文字の共通性があるんですけども、英語をずっと勉強してきた日本の大学生にとっては、英語の次に学ぶ外国語としては多分非常にとっつきやすい言語なんじゃないかと思います。
ただ、多かれ少なかれヨーロッパの、イタリア語、フランス語と共通するところだと思うんですけども、例えば英語にはなかった名詞の姓に種類があるとか、ヨーロッパの言語っていうのは、大体二人称というのが英語はyouだけでしたけども、大体二つ、2種類あると。確かイタリア語でも、
まぁ同じ。
そうですよね、基本的に。フランス語でもそう。
ただ使われるものがちょっと違いますけどね。ドイツ語では「彼らSie」というのを敬称「あなた」に当てますが、イタリア語では「彼女」Leiを当てます。
二人称に2種類あるというふうな点とか、学生の人たちはずっと英語を勉強してきたのに対して、英語というのはある種シンプルに単純化されているんだなというイメージを、ドイツ語を勉強すると持つんじゃないかと思います。それは逆に言うと、ある種文法がもう少し英語よりは体系的になっている。
それは確かに体系的に学ぶんで、なにかしらの労力と時間が必要なんですけども、それを学ぶと、これはさっき服部先生がロシア語に関して言われてましたけど、最初の文法はそういう意味では英語よりも大変っていうところがあるかもしれないんですけども、それをとりあえず勉強すると非常に体系的になっているのが分かる。そういう意味では、理系の学生さんというのはひょっとしたら比較的英会話とか言語が苦手だという学生さんが多いかもしれないですけども、そういう学生さんにとっても、丁々発止の議論をできるようなレベルにはなかなかなるのは、非常にどの言語でも難しいと思いますけども、その文法体系を理解するという点では比較的、むしろ英語なんかよりも体系的になっている部分があるので学びやすい言語なんじゃないかなという気がします。とりあえずそれくらいで。
 イタリア語ですけれども、先ほどロシア語の服部先生が最初は坂が非常に急だけれども、登り切ってしまえばあとは割と平坦な道になるとおっしゃいまして、これは色んな人がおっしゃることなんですが、イタリア語はその逆でして、最初は坂とも思えないほど非常に楽ちんで、文字の場合ですと、例えばローマ字って言いますけれども、ローマ字というのはそもそもローマの字なわけでして、要するにイタリア語はあの通りと思って頂ければいい。それから文法に関しましても、これは先程ドイツ語の奥田先生もおっしゃたように、ヨーロッパの言語でしたら大体似たようなものだということで、イタリア語が特別に難しいということはありません。それはないんですが、問題は先程話題になりました格変化というやつです。
イタリア語ですけれども、先ほどロシア語の服部先生が最初は坂が非常に急だけれども、登り切ってしまえばあとは割と平坦な道になるとおっしゃいまして、これは色んな人がおっしゃることなんですが、イタリア語はその逆でして、最初は坂とも思えないほど非常に楽ちんで、文字の場合ですと、例えばローマ字って言いますけれども、ローマ字というのはそもそもローマの字なわけでして、要するにイタリア語はあの通りと思って頂ければいい。それから文法に関しましても、これは先程ドイツ語の奥田先生もおっしゃたように、ヨーロッパの言語でしたら大体似たようなものだということで、イタリア語が特別に難しいということはありません。それはないんですが、問題は先程話題になりました格変化というやつです。
今の初修外国語の中では一応格変化があるとされているのは、多分ロシア語、ドイツ語、アラビア語と、そんなところだろうと思います。イタリア語にはないということになってるんですが、ないというのは額面上のことでして、スピリットといたしましては、あるんです。先ほどのラテン語やギリシア語が基にあるのだからそうなってるんだという話がでてましたけれども、そういう意味でスピリットの面でラテン語に一番近いのがイタリア語かもしれません。
確かに形の上では格変化というものはないんですが、スピリットの上ではある。これはどういうことかと言いますと、名詞をそれ一つだけ取り出しても、それが文の中で主語になっているのか目的語になってるのかということがわかるということです。例えば人の名前なんかでも、カエサルというような人がいましたけれども、実際にはカエサルという名前だけを表現する方法はないんで、カエサルが、カエサルに、カエサルを、カエサルの、カエサルよー、とかいうこういう形でしか単語が存在しないんです。こういうことは代名詞については現在でも色んな言語に言えることで、英語でも私という単語は英語にはない。Iっていうのはありますけど、あれは主語になるということが運命づけられてまして、ですからIとmeの違いは何なのかというのはその格変化の違いというのが実態です。イタリア語の場合、この格変化が額面上は一応消え去ってるんですけど、スピリットの上ではある。つまり、単語一つを聞いただけで、それが主語なのか目的語なのか何なのかが分かるはずだという考え方で文ができてます。
こうなりますと、非常に語順が自由。英語ではSVOとか、SVOCというような文の構造を習ったと思いますが、イタリア語を含めましてたぶん西洋の言語は大体似たような構造を取ってます。ですが、語順が自由ということは、SVOっていう形の文が順列組み合わせで6種類、SVOCなら12種類出来るという事になるわけでして、イタリア語はそういう言語なんです。文法は割と簡単、発音はもっと簡単、すごく楽勝に見えるんですが、それだけではなかなか実際のイタリア語が分かるようにならないという印象を受けるわけです。
これにつきましてはまた後程も回ってくるとは思いますけども、実用語なのか文学用語なのかという違いもありまして、そういうこともあってイタリア語は出だしは非常に楽なんですが、いつまでたっても終わらないという感じがします。これは苦労が続くというよりは虜になるという性質でして、いったん始めるともうやめられなくなる、魔力みたいなものがあります。
ただし、とりあえず初修外国語として勉強する段階ではその楽な部分を享受して頂くということが可能です。そして、それだけで終わりにする気がなくなった私のような者はいつまでも勉強を続けるということになります。それでも決して苦労をする訳ではありません。楽しみが長く続くという感じですね。
岡先生お願いします。
アラビア語はロシア語と同じく最初は急な坂で、その後もあまり平坦にはならないかもしれませんが、とりわけ最初が苦労します。その一つがアラビア文字、私たちが慣れ親しんでいるローマ字とは違うアルファベットだということもありますが、でもアラビア文字は28文字しかないので、覚えるだけだったら1週間あれば十分です。発音も簡単です。日本語にない子音もありますが、子音の発音で苦労する人はいません。
そしてアラビア語の母音は3つしかないので、とても簡単です。アラビア語という言語の特徴として、まず比較言語学的にはヘブライ語と同じセム系の言語なので、三語根、つまり三つの子音の組み合わせが意味を担い、この三語根の動詞を基本に、さまざまな動詞や品詞が派生して意味世界をつくっています。辞書も三語根を中心に編纂されているので、意味の分からない単語を辞書でひくときは、文法知識を駆使して、一旦それを三語根に還元しないと辞書が引けないんです。
三語根というのがよくわからないんですが。
三つの子音の組み合わせです。例えばDRSだったら「勉強する」ということを意味していて、このDRSに接頭辞や接尾辞その他がついて「勉強する」に関連するいろいろな意味の単語が派生しています。「マドラサ」は「学校」、「ディラーサ」は「研究」、それから「ダルス」は「レッスン」といった具合です。また、KTBは「書く」を意味していて、「マクタブ」というと「事務所」、「キターブ」というと「本」、「カーティブ」というと「作家」を意味します。ある単語に三つしか子音がなければ、三語根はこの三つだとすぐ分かりますが、派生形だとか不規則動詞だとかありますので、それらをしっかり覚えないと三語根は分かりません。だから、ほかの言語では、辞書を引いて文章を読めるようになる、というのが初級の達成目標だとしたら、アラビア語の場合は、辞書を自分で引けるというのは、文法をほぼすべて習得しているということなので、アラビア語的にはすごいことなんです。初級では、単語を見て、この形は何だ?動詞なのか名詞なのか形容詞なのか、動詞なら完了形なのか未完了形なのか、そして接尾辞とか接頭辞など余分な枝葉を刈り取って、そこから三語根を復元して初めて辞書が引ける、だからよく授業では検視官に例えていて。
検視官?

原形をとどめない遺体が発見されたときに、いつ、どのように殺されたかといったことを遺体の状況から特定し、身元を明らかにする、という検視官の作業です。
アラビア語を学ぶコツとして学生に言っているのは、分からないのを楽しむということ。複雑怪奇に変形した遺体から、これは誰で、どこで誰にどのようになぜ殺されたのかというミステリー小説だと考える、ということです。最初の1ページで犯人が分かってしまうようなミステリーは面白くないのと同じように、分からなさを堪能するのがアラビア語を学ぶおもしろさと思えば、アラビア語の勉強も楽しくなります。
それから社会言語学的には、アラビア語は「ダイグロシア」と言われている二言語併用です。同じことを異なる言語で同じように話せる「バイリンガル」とは異なって、「ダイグロシア」の二言語併用というのは、それぞれを使用する局面が社会的に完璧に分かれています。私たちが授業で学ぶのは「フスハー」と呼ばれる正則アラビア語、文語なんです。この文語はアラブ世界どこでも共通しています。しかもそれは、文法的には7世紀にクルアーンが読まれた当時と基本的に変わってないんです。だからこのフスハーを学ぶと、アラブ世界のどこに行っても新聞や小説が読めて、ニュースを聞いて分かる。あるいはいつの時代に書かれたものであっても、基本的に文法は同じなので読むことができる。でも、それはあくまで文語の話であって、話し言葉は国によって地域によって全然違うんです。
学生時代、アラビア語の文法を四苦八苦して覚えてる時に、先生がふと、でもこれを勉強してもアラビア世界では話されてないんですよね、ってぽろっとおっしゃって、突然奈落の底に突き落とされたような気がしたことがありました。初修外国語の初級の到達目標としてたとえば日常的な買い物ができるレベルの会話力がある、とか設定されると、アラビア語の場合、フスハーを使って買い物などしないんです。こういうことを言うと、話すことができないなら、アラビア語はやめようと思う人が多くなってしまうかもしれないんですけど。でも、買い物はできなくても、教養ある外国人として、教養ある人たちと教養のある話はできます。
もう一つ私自身が認識を新たにしたことがあるのですが、アラビア語を一年間、ちゃんと勉強してきた学生は、アラビア語は難しくないと言う。すべて三語根が基本になっていて、それを覚えるだけでいい。毎回課題さえこなしていればアラビア語はヨーロッパ系の言語に比べて難しくないと。動詞も完了形と未完了形しかないんです。
先程、服部先生が活用のことをおっしゃいましたけど、アラビア語の場合は、彼・彼女・あなた女性・あなた男性・私と、単数と双数と複数形があるので、全部で13通りの活用があります。13というのはヨーロッパ系の言語に比べると多いかもしれないけれども、完了形と未完了形しかないので、例えばフランス語の中でいろいろな時制のアスペクトがあるのに比べたらはるかに簡単です。なので「アラビア語が難しい」と言っている学生にとって何が難しいのかというと、おそらくアラビア語という言語がむずかしいのではなくて、日々きちんきちんと課題をこなすということが難しいのではないかと思います。多分そういう人たちはどの言語をとっても難しいのではないでしょうか。
先程服部先生が言われましたように、このあとは各言語の魅力というか、どういう世界が見えてくるよとか、そのような話をしていって頂ければいいかなと思うんですけど、今、岡先生の話を聞いていて、アラビア語は私全然知らないんですけど、三語根というのはおそらくユダヤの言語も。
セム系言語の特徴ですのでヘブライ語もそうです。
ユダヤ人の、ヘブライ語も同じですよね。その辺のものを昔読んでいた時に、子音とdrkとかいう子音と、その間にどういう母音を入れていくかというパズルみたいな形で色んな意味合いが作られてきて、例えば庭とか世界とかいう、それの語根がこれだったとしてということで、そこから色んな世界が広がっていく。そしてまたもう一つ別のことで、一つの書物とか文面があったときに、その語根がなんかの仕方でちりばめられてるというような読み方が宗教的にはあったりするんです。そのような言語の構成要素に対するものすごい自由な関わり方というのは、今のヨーロッパの言語にはないような感じで、すごく面白いなと思ったんですよね。
すみません、一言補足させて頂くと、今多賀先生がおっしゃったように、アラビア語は基本的に子音だけで綴られるんです。さっき言ったktbにしても、そこにどういう母音を込めて読むかによって動詞になったり、名詞になったり、形容詞になったりするので、さっき申し上げた辞書が引けないというのは、ヨーロッパ系の言語だったら子音と母音が分かれているから、単語が出てきた順番に辞書が引けるんだけれども、文法がわかってないとそこにどういう母音を入れたらいいのかが分からないので辞書が引けないんです。