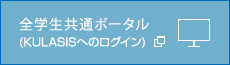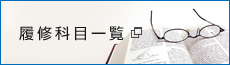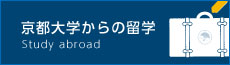第1回 初修外国語担当教員による座談会

天野先生がおっしゃったことにまったく同感です。私たちは英語をツールの言語として勉強していると思うんです。とりわけ英語がグローバルランゲージとなっている今は、英語ができるというのは、必ずしも英語を母語とする人たち、英語のネイティブと話すためだけではないですよね。それに対して初修外国語、英語以外の言語を学ぶというのは、ツールとしてその言語を身につけるということよりも、寧ろその言語が生きられてる世界、例えばアラビア語であれば、アラビア語を生きている人たちの世界に触れる、その人たちについて体験的に知るということだと思うんです。
学生たちの感想を読むと、アラビア語をとって良かったと書く学生たちも大勢いて、なぜ良かったかと言えば、異口同音に「世界が広がった」、「アラブ世界が身近になった」と書いています。単にアラビア語の文法と単語の意味を覚えるだけでは世界は広がらないはずです。アラビア語を学ぶことを通して、アラビア語を生きているその人たちの世界観に触れるからこそ自分の中にあった世界が広がるということだと思うんです。
先程、天野先生がコーヒーを例におっしゃいましたが、例えばアラビア語でパンのことを「ホブズ」といいます。辞書を引けば、「ホブス」=Bread と書いてある。「ホブズ」の意味を「パン」と答えた学生には、今どういうパンを想像したかつっこむと、たいてい、四角い白いパンとか長いパンとか、答える。でも、違う、アラビア語のパンていうのは平たい座布団みたいなパンなんです。「ホブズ」=「パン」じゃなくて、あの座布団みたいなパンを食べてみないことには、「ホブズ」とは何かということはわからないと思うんです。単に食べただけでもだめで、やっぱりアラブ社会の中でアラブ人と一緒に食べて初めてホブズの何たるかが分かる。そういう「生きられている意味世界」を経験として学ぶことが初修外国語を学ぶということの大きな意義としてあると思います。だからコンピュータを使った学習というのは、ポジティブな側面も認めつつ、個人的には、初修外国語を学ぶということは、先程多賀先生が実際に謦咳に接するということの重要性についておっしゃったように、そういう形でしか伝えられないものというのがいっぱいあるんじゃないかと思います。
それからもう一つ、英語がグローバルランゲージになっているから第二外国語はもう要らない、ではなくて、だからこそ逆説的にも、第二外国語というものがますます重要になっているのではないか、と思います。単に教養として英語以外の言語をかじってみるというだけでは、不十分になってきている気がするんです。等しく皆が英語を使いこなせるような時代になりつつあって、それが望まれているからこそ、英語以外の言語を英語と同じくらい使いこなせるだけの力が以前にもまして必要とされているのではないかと思います。
おっしゃる通りですよね。これは僕らも、例えば同級生なんかで、昔あった東京銀行に就職する時に、英語ができて当たり前、英語ができて他に何ができますかって、ロシア語ができる、採用と。そういうことがこれからますます増えるでしょう。
最後、時間もちょっとあれなんで、今その外国語を学ぶ価値とかそういう意義はそうだろうし、先生方の間で共有されているんで今更念押しすることはないですが、ちょっと学生さんの立場に立って、さっきから理系の諸君か文系の諸君かという話が出てくるんですが、根本的にはあまり意味がないことだと思うんですが、ただ新入生の諸君は、学習の手引とか見て、クラス指定の授業って折り込みでみると、工学部の例えば1組と2組のところと、法学部の1組と2組と比べて、クラス授業とか全然違うんです。
法学部って英語とドイツ語くらいしか、スカスカなんですクラス授業。工学部、びっしり物理とか数学とか実験とか。だからその時点で見てる世界が違うというか、いい悪いじゃなくて、工学部の人とか、あるいは人間健康科学科の人とかものすごく忙しいんですよね。だから外国語が難しいんじゃなくて、岡先生がおっしゃったように毎日15分課題を解く時間をとることが困難なんで、ある外国語が難しいとかそういうことじゃなくて、そこで我々教員が心掛けたいというか、少し頭を、我々が外国語を習った頃と考えを変えて、皆が皆、専門家になるわけではないので、外国語を勉強するときの情報ってすごく多いんですよね。その情報過多にいってはいけないので、情報過多は混乱のもとなので、できるだけ1回生の諸君に教室で教える情報を絞り込む。
例えば外国語教師としてはここはこうなんだけど、こういう例外があってとか、この場合は前置詞は普通こうなんだけどこういう決まった語句の場合には前置詞が例外でこっちにくるんだよとか、この場合はちょっとスペリングが例外でこうなるとか、語学の教師としては教えたくなるコツは色々あるんだけども、そこを1年生の人たちにやってると、特に理科系の人なんかは積み重ねて理屈っぽくいきたいんで、こだわっちゃう。そこでつまずくと言わないが、嫌な感じを起す。そこで情報を絞り込んで、ある意味、必須事項だけのものすごく薄い教科書を作るというのは我々教員が心掛けていいと思うんです。
手前味噌じゃないですけど、ロシア語の場合には実は何年か前から作ってあって、ものすごく薄い。学生からNHKのラジオテキストより易しいと言われるような、語彙数で言うと250語。250語のボキャブラリーって少ないです。でも250のボキャブラリーをきちんと覚えて使いこなせると、運用的には3倍くらい、750くらいの運用的な価値があるので。250語しかない教科書は48ページしかないんです。
でもその薄っぺらい教科書なんだけど、情報を絞り込んでやると理科系の方も皆ついてきますので、文系・理系という分け方にこだわらなくて、非常に情報を整理して絞り込んだ教材を作って、1回生においては文理問わず提供して、2回生になってより専門基礎的につなげていく子はもうちょっといけるんじゃないかと。
そういう整理の仕方はこれから教員の方が心掛けられたらというのは、提案というかどうでしょうかという意見ですが、どうでしょう。ドイツ語なんかは必ず接続法第2式までいけとか決まりがあるんでしょうけど、その時に。
そうなんですね。他の大学ではそこまでいかずに接続法は省きますっていう方が今圧倒的に多いんです。理系クラスの場合などこれは検討する必要があるかもしれませんね。
玄関の入り口さえわかればいいんで、ここは鍵が開いてあとは自分でやれると、その時にどこから行けばいいっていうところまで、その整理とか、それはかなりいける、まだ検討する余地はあるような気はしますよね?おっせっかいみたいなこと。
いかがですか?ドイツ語の場合は。
そうですよね。京大もさることながら、我々教員の姿勢としてもどうしても、私なんかも特にそうなんだと思いますけども、やっぱりあるクラスの、こちらの目としては比較的興味を持っていてよくできる学生さんに向けて授業をするという姿勢にどうしてもなってしまうんですね。もともと興味が無かったり、苦手だという学生さんにも少し目を向けるという、そういう配慮は多少今までは欠けていたかなという気はします。
これは大学の先生一般に、語学に限らずそうだと思うんですけども、どうしてもよくできる学生さんにできるだけたくさんのことを教えた方がいい授業だっていうふうについつい我々は感じてしまうんで、そこら辺りを反省する余地があるんじゃないかと思います。