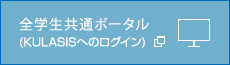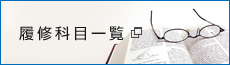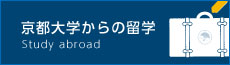第2回 初修外国語担当教員による座談会

私は実は三輪先生と同じ歳で、去年の3月で医学研究科を定年退官して、4月からこちらの国際高等教育院にお世話になり、英語部会長を務めさせて頂いております、武藤と申します。ムトウと書きますけど、タケトウと読みます。
医学部の学生のとき交換留学生として米国の大学でしばらく学び、帰国して京大を卒業し、大学院を修了して学位取得直後に、再度米国に留学して博士研究員(ポストドク)、助教授、准教授まで14年間、米国の大学と研究所で研究活動をしました。 そういう経験もあって、英語と英語教育に強い関心があります。 アメリカ英語っていうのはもともとイギリスから来たわけですが、米国人は一般に英語と英語教育に関して非常に強い関心を持っていて、テレビでもよく話題になり、本も沢山出ていて、私もそういう機会に色んな知識を得ることになりました。先ほどお話があったように、語学っていうのはその文化を背負ってる。その文化は多くの歴史を背負っているわけで、歴史を無視して言語を語ることは出来ない。英語の歴史を勉強してみるとそれはイギリスの歴史の勉強をすることになるわけですけれども、英語っていうのは非常に特殊な言語だということが分かります。則ち、ヨーロッパの言語の殆どがその中に入ってるんですね。
もともと住んでたケルト人のケルト語に始まって、その後アングロサクソン民族が所謂「ケルマン民族の大移動」で東から侵入してきて、その後何度もデイン人が北東から攻め込んでくる。その後にはノルマン人が南から攻めてくる。230年間もノルマン王朝が続いて、政府の上の方はみんなノルマン語(フランス語の方言)になっちゃった。一方キリスト教の普及で聖書としてギリシャ語やラテン語が入って来る。ですから英語を深く勉強しようと思ったらフランス語やドイツ語を勉強することも非常によく役立つし、ラテン語やフランス語以外のラテン系の現代語(イタリア語、スペイン語など)のルーツも沢山入っている。ギリシャ語も沢山入っている。そういうふうに英語を見るようになって初めてね、英語だけ勉強してたら英語が分かるということではない、色んな言語を勉強することが大事なんだと認識するようになりました。
それから東洋の言語はどう捉えたらいいのか考えてみましょう。例えば韓国語が難しいと思うのは字(ハングル)が読めないことです。字の読み方や発音の仕方が分かっても、今度はその背景にある元の漢字が分からない。韓国語ではその元の漢字を 韓国風に読んでるんですよね。我々が漢字を日本風に読んでいるように。文法は日本語とほとんど同じで、元になった多くの漢字も共有しているんですけれども、現代韓国語からはその共有部分が抜けていて難しく感ずるのだと思います。西ヨーロッパの言語は、私から見たらもう方言に近いですよ。
そうそう、同じようなラテン語が崩れているだけですから。
だからそういう意味で「多言語主義」ということを沢山の人が唱えていて、京大の先生方も 、加藤周一も書いているけれども、多くの言語をある程度勉強してみると、それが幅広い国際理解に繋がるというのは西洋社会では当たり前として通っていると思います。それから東洋でもやはり漢字文化圏というものが歴然としてあると思うんですね。韓国では崩れつつあるのかもしれませんが。少なくとも我々が使ってる文字はやはり中国の方から来てるわけです。ドイツ語にしてもアルファベットで書いてはいるけれども、歴史の本を読むと、ゲルマン人は古代日本人と同じで、文字を持っていなかった。読み書きが出来なかったって書いてあった。ゲルマン民族が攻めてきた頃(4~5世紀)の話ですよ。
ものすごい前ですね。
そうそう。だけどローマ人は初めからちゃんと文字を持っていた。ローマの文化を「グレコローマン」と言うように、ギリシャを取り込んでしまったわけですよね。あれは非常に不思議なことで、初めはギリシャが栄えていたけど、結果的にはローマ帝国に征服されて、ローマ人はギリシャ人を奴隷にしちゃったって書いてある。だけどね、よく調べてみるとギリシャ人を自宅に住まわせて、家庭教師として自分の子供にギリシャ語を教えさせたりしてるわけですよ。近現代の帝国主義支配とはかなり違う。それはやっぱりギリシャが持っていた文化をローマ人が非常に高く評価していたということなんですよね。
そういう事実を色々学んでいくと、文化の歴史っていうのは非常に面白いし、言語を通して歴史を学ぶと深い理解ができることが分かってきます。私が国際学会なんかでアメリカやヨーロッパの人達と専門外の話をしたときに気が付くことは、日本の教育で最も遅れていることの一つは、外国語を含めた教養教育だと思うのです。残念ながら我々が育った時代は高度成長期の理数科偏重ですね。「追いつけ追い越せ」型の理数科偏重教育で、単なる道具としての受験英語教育。だけど日本も多少成熟して先進国の仲間入りをして、京大の卒業生が国際社会で話す機会が増えて来ていますが、単に英語を喋れるから信頼され、リスペクトされるかというと必ずしもそういうことはない。
一方、欧米の歴史、それを複数の言語を含めて理解し、その中で自分や自国の立ち位置を俯瞰できている人たちは、言語が出来るということを越えてね、人間としての信頼やリスペクトを得るところに至ると思います。それは日本人だからとか中国人だからとか韓国人だからとかっていうこととは殆ど関係ありませんね。それくらいの教養を身に付けた人たちが欧米には沢山いるし、アメリカの官僚なんかでも東洋の言葉と歴史に対して非常に明るい人がいっぱいいます。第一次オバマ政権の財務長官をした、ティム・ガイトナー。あの人はニクソン大統領が初めて中国に乗り込んで国交回復したときに、米中間に交換留学制度が出来て、米国からの初代の交換留学生でした。だから中国語ペラペラなんですよ。ですがそういうことを大っぴらには言わなくて、財務長官として中国に行ったとき、中国政府の官僚達は (外務省にあたる)国務省の役人ならともかく、財務長官が中国語が出来るとは思わなかったらしい。その官僚達が中国語で彼の面前で噂や悪口も含めていろんなことを平然と喋っているのが分かったって書いてありましたから、米国にはそれくらいの背景を持っている政治家や研究者が少なからず居て、それが米国社会を支えているのだと思うし、日本にもそういう人材が必要だと思います。
英語の勉強に関しては、例えば第二次大戦中の日本では敵国語だから英語使っちゃいけないって言われたらしいんですけれども、米国ではミシガン大学で有名な「ミシガン・プラクティス」っていう方法が開発されてですね、それで日本語を勉強して情報作戦を立てたわけですよ。「この電車は渋谷に行きますか?」っていう合言葉を作ってですね、敵国語である日本語をとことん勉強した。その方法の一つは先生方もご存知かもしれませんけれども「ミムメムメソッド」(mim-mem method; mimicking-memorizing method) と言って真似して覚える方法です。夏休みの雲ヶ畑の合宿の時にそれを習いました。
それを使ってた。
それを使ってた。だから知ってるんです。
なるほど。
そういう話いろいろあって、語学の重要性あるいは多言語主義っていう考えが非常に重要だという認識があって、この職をお引き受けしたということもあります。ただこれは、表向きの大義名分ですが、実はそういうことよりも、平たく言うと私は色んな国の人と色んな言葉でしゃべれると非常に楽しい、これは素晴らしいという感じが英語を基にしてドイツ語や、片言のフランス語でも喋れれば大変楽しい。それがとても大事なんじゃないかと思います。