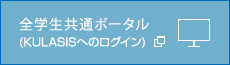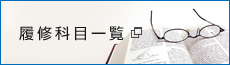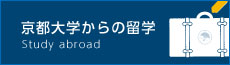第2回 初修外国語担当教員による座談会

初修外国語、つまり英語以外の言語と英語を学ぶ時の一番の違いとは、大学入試の有無だと思います。初修外国語を学ぶときには入試のために学ぶのではないのですね。初修外国語学ぶことのもう一つの大切な意義は学びの学びに関係しています。
現在、世界は知識社会になっていて、学校だけではなく、生涯にわたり学び続けることが重要になってきてる。それで学校が終わったらもう学びが終わりではなくて、むしろ学校終わってからも職業人として新たなことを学ばなければならない。初修外国語を学ぶことは、単に文法の知識を学ぶことだけではなく、何かを学ぶ手法、学びを学ぶということと関係があります。
そうですね。
単に人から受験勉強として課題を与えられて、そこに到達することだけではなく、自分で目標を設定し、自分で勉強のリズムを身につける。そして、勉強の仕方を考えること、例えば自分は辞書を使うのがいいのか、あるいは文章を暗唱するのがいいかなど、自分にあった勉強の仕方を学ぶこと。私はこれを外国語の学習を通じて学んでもらいたいと思います。
それは答えは一つじゃないんです。
これまで高校までに学んできた英語の勉強法を見ると、上から与えられたものをこなしていくことが学習の中心だったと思います。ところが、大学の初修外国語の学習は、これまでの英語と比べると、受験のような直接の目的のない学習に見えるかもしれません。初修外国語を学ぶ意味とは、言葉を学ぶ、あるいはその他のなにか新しいことを学ぶことはどのようなことなのか、これを学ぶことも、つまり学びの学びもまた、外国語学習の重要なポイントだと思うんですよね。
スキル的なことがあるから、わかりやすいんですよね。自分でどれぐらいできるようになったかっていうことは。
京大の伝統には自学自習が掲げられています。そしてこれと似た意味で、自立学習もまたはよく言いますが、この場合の自立とは自分で立つという意味で使われていると思います。ところが、ヨーロッパで考えられているオートノマス・ラーニング(自律学習)とは、単に教師からならうのではなく、自分一人で進める独習という意味でもありません。自分で目標を立てて、自分でどのような教材を選んで、自分でカリキュラムを作って、自分で評価を行う学習です。自分の力で、自分に合った勉強の仕方を開発するのです。そのために外国語を学ぶことはたいへんに重要だと思います。
大学教育を終えて、社会人として何かを学んでいくとき、外部の人の行うテストによって評価を下すだけでなく、自分でどこまで分かったかといった自己評価が重要になります。外国語を学ぶ時にはテストをやりますが、それだけではなくて、自分の到達目標を立てて、そこに到達したかどうかとの自己評価を行うことは、外国語を学ぶうえでとても大切なことだと思います。
この時期にやるとすごい意味ありますよね。この18から。
そうですよね。本当に砂漠が水を吸い込んでくように吸収できる時期、本当に。
あれ、おかしいって思いますもんね。昔はもうちょっと覚えることができたのに、って。この若い時期は本当に貴重です。
私と武藤先生以外は、みなさん文系と思いますが、理系の学生、例えば数学やりたいとか物理やりたいとか、工学部だったら機械に興味があるとか、そういう学生にとっての勉強の仕方は、どうなんでしょう。それとも何かヒントになるようなことはありますか?
フランス語の場合では、理系はCALLという、コンピューターを使った学習法を採用しています。その学習サイトはメディアセンターや出版社のサーバーに置いてありますので、教室外でどこでも勉強出来るわけです。そのため、自分でリズムを作って勉強をすることが大切です。毎日15分勉強したいと思えば、毎日15分やればいいし、週1回1時間や2時間やりたいと思うんだったら、それも良いでしょう。学習のリズムを自分で作ることができるのです。もちろん、授業の中で翌週までの宿題や課題を出します。
学習のリズムや学習の場所について、今ネット上でどこでも出来るような体制がありますので、それは理系の学生にとっても、すごい便利になっていると思います。そのために他の専門の勉強との関連から自分の学習のサイクルを作るということに役立つと思いますね。ネット上でのフランス語の問題では3回間違えると解答が出てきます。ですので、ちょっとゲーム感覚のようなところもあります。対面型の授業では、教師が話していて、教師のリズムに合わせなきゃ分からないこともあります。ところがネット上の学習には、自分で何回も読んだり、繰り返しできるという利点があります。ですので、物事の飲み込みの早い人や遅い人のいずれにも対応しています。また練習問題は段階を追っていて、基礎的な部分とそれからもう少し難しい部分ともう少し更に難しい部分に分かれています。つまり最初にやる時は一番やさしいとこだけをやっていって、それが終わったらもう少し応用問題をやるというふうに自分のペースに会った学習を組み立てることもできます。このような点が理系の学生にも適切なのではないかなと思います。
その理系の学部でやることっていうのは、例えば今から4年間でやる専門課程の勉強の内容というのは例えば10年後はどうなんですか。一番基礎の部分は変わらないと思うんですけど、つまり有効性がどれぐらい。例えば先生方が30年前とか40年前に勉強された学部の勉強というのはもちろん基礎の所は変わらないと思うんですけど、そこから先の部分というのは今どうなのでしょうか。

医学の分野だと、最も基礎的なところは同じですよ。 例えば40年経ったからその間に人間が進化して人体の構造が変わるわけではないんですけれども、実際に教授している内容はかなり大幅に変わっています。だから知識として詰め込んだものが将来ずっと役に立つかというと必ずしもそうではありません。大学で知識を全部教えても、10年も経ったら古くなるので、それに対する反省から欧米の大学の医学教育では変革があって、知識を教えるんじゃなくて、先ほど西山先生がおっしゃったように、どうやって新しい情報を自分で集めて、その情報を自分で評価して自分のものにしていくのかという、勉強の「方法」を教えるべきだという考え方が15年ぐらい前から米国ではかなり行われまして、教室でやる講義をかなり減らして、4割とか多い大学では6割ぐらいは、いわゆるチュートリアルという形で少人数で演習させる。学生同士が自分達で勉強する、先生はそこにいてガイダンスはするけど直接板書をして講義はしないようになったんですね。確かにそれは 非常に有効な教育なんですけれども、一つ大きな問題があって、それにはすごく多数の教官が要るし、時間もかかる。米国のアイビーリーグなんかだと日本の大学と比べると、学生当たりの教官数が8倍とか10倍とかいますので、そこでは出来ても日本の大学では非常に難しいという現実があって、日本では導入しても量的には1割にも達していません。
もうひとつは米国でそういうことを10年ぐらいやって、それでもやっぱり基本的に体系化して教える方も大事だという批判が出て、チュートリアルの比準は今ちょっと減って、講義を8割ぐらいに増やすという逆戻り現象もあると伺っています。重要なポイントは私が40年前に習ったことが今現場で全く同じかというと、かなり様変わりしている。それは確かです。例えば我々の頃は胸部のレントゲン写真1枚を見て、その1枚から細かいことを全て読み取るという訓練を受けたわけですけど、今はそんなことやってる暇にCT撮りなさいと。CT撮るともう立体像でというか全体を縦横無尽に切った情報が一度に撮れて、それを瞬時にわーっと連続に映して動画のように見ることもできるので、直ぐ分かっちゃうということがありますので、確かに、知識を教えてもすぐに古くなってしまうという側面はあります。でもそれは技術革新の著しい専門知識のことで、逆に語学とかの分野はそうではないですよね。
そうそう変わると困っちゃいますから。10年前に習ったスペイン語が通じないとなると困っちゃいますから。
だから初修外国語の場合、文法とか基本的な単語を最低限覚えるところは、やっぱりこれは避けては通れないと思うので、しんどい思いをして一刻も早くやった者勝ちと、私は思いますけれども。
ただ英語と、例えばドイツ語とでも全然違う。ドイツ語の先生が書いておられるし、英語で論文の原稿なんか書いてて思うんですけれども、イギリス英語の変遷を見ると、どうやって今の英語が出来たかっていうことが、よく分かるんですね。例えばノルマンが攻めて来たのは1066年ですか。
そうです。
ノルマンが攻めて来る以前に使われていたイギリスの英語というのはオールド•イングリッシュといいますけれども、文法的にも今の英語よりずっと複雑で語尾変化が著しかった。現代ドイツ語では残っている、間接目的語をとる与格(dative case)とか、 具格 (instrumental case) っていうのがあって、例えば「ペンで」書くは、現代英語ではwith a penと、前置詞を使いますが、前置詞を使わずに語尾を格変化させた。
まとめますと、ケルト語に始まってゲルマン系のアングロサクソンの言語、フランス語系のノルマン語、ギリシャ語やラテン語の要素などが沢山入って来て、そのため語彙が大きくなって語数が増えてしまった。フランス語の3倍、ドイツ語の2倍とかに、ものすごく増えてしまった。その一方で文法は非常に簡単になっちゃった。じゃあ単語さえ沢山覚えたら英語は書けるかというとそうではありませんので、ご存知のように、格変化を非常に簡略化してしまったために、語順が極めて重要になった。
ドイツ語の日常会話ではよく倒置をしますけれども、英語でそういう倒置をしちゃうと主客が転倒して意味が変わってしまうということはありますよね。だから英語で論文を書くときに英語らしい表現というのは非常にストラクチュラル、きちんとした構造で、同じ単語を繰り返さずに語彙を変えて表現するというのが英語らしい表現になります。ドイツ語のような英語を書かれると、英語圏の人は分かり難いし、いらいらしちゃう。ずーっと長い主語句が続いて最後に動詞が来るっていうのは、それはもうだめですよね。だから結論を先に言うってさっき先生おっしゃったけど、まず短い主語があってすぐ動詞が来ないと分かりにくい。ドイツ語を少し勉強すると、格変化による語尾変化が非常がはっきりしているので、倒置をしても意味が通ずるわけですけれど、そういうところが気がつくと非常に理解しやすい。
国際学会などでは、様々な訛りの人をしょっちゅう聞きますよ。英語圏でも例えばアメリカの英語もあればインドの英語もあればオーストラリアの英語もあれば、ましてやフランス語圏の人も学会では英語で発表します。そうすると少しでもフランス語勉強してフランス語の発音が分かっていると、フランス人の英語が良く分かる。それ知らないと全然わからない。ということはあります。
対応力がつかない。透けて見えない。
TOEFLの試験。先日、国際高等教育院の委員会で実際の試験を聞かせて頂いたんですが、あんなに綺麗な発音であんなにゆっくり話してくれる人はアメリカ人でも滅多にいません。あの2倍ぐらいのスピードで、多くの場合何らかの訛りがある。東部の訛りだったり南部の訛りだったり、ありますよね。だからそういう意味ではやっぱり色んな言語に触れておくということで、分かり易いということはあります。英語中心的な発想ですけど。
あと、私は、以前工学部の建築学科の学生に中国語を教えてたことがあるんですけど、今は理学部薬学部の学生に教えたりもしてるんですけれども、そういう学生に最初のほうよく聞いたんですよ。君たちなんで中国語選んだのか、単位取りやすいと思って選んだのか、って意地悪く聞いたのです。そうしたら建築学科の学生が真面目な顔して、いや僕たちはこれから中国に建築で建物建てたいんだ、と答えるのです。規制が日本と異なるので、チャンスがいっぱいあって、好きな建物が建てられる、というのです。
中国はものすごい建築ブームでしょ?