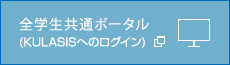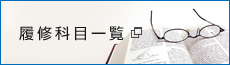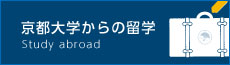第2回 初修外国語担当教員による座談会
それではこの辺から、我々同士の話ではなくて、新入生のことを考えながら話をしましょう。履修に際してアドバイスがあれば、なにかそのへんをまずお願いします。

京大の学生、特に理系学生は、英語だけを学べばよいのではないかと考える者もいると思います。
確かに理系、とりわけ数学を学問の基盤にするような学問からみると、言葉とは道具にすぎない。だから、道具はどれを変えても同じ内容を伝えられる。H2O(水)はどこにいったってH2Oです。ところが、これが人文科学や社会科学の一部、要するに数学を必ずしも基盤としない研究や、あるいはその学問が英語圏以外のところで生まれた学問を考えるとき、言語の違いがものの考え方に深く結びついていることがわかります。例えば経済学や経営学といったアングロサクソンのイギリスで生まれた学問を取りあげてみましょう。日本では90年代から日本経済学会は学会誌を英語だけで刊行しているんです。経済学の研究者にとっての共通言語とは数学であり、英語です。そのために、英語だけわかれば、全てわかるというふうな理屈が成り立つかもしれません。ところが他の学問は、学問の創られた土地によって、何を問題とし、何を問題としないのか、これらの問題意識そのものもかなり変わってきます。
ところが、英語だけを勉強していると、世界はみんな同じようなものの見方をするのだと思い込みがちです。ですが、他の言語を勉強し、特にその言語を使ってなんらかの専門の勉強をすると、物の見方というものがあきらかに違うことがわかると思います。英語の世界、アングロサクソンの世界は、効率的な物事の見方に関心を寄せます。ところが、このことは他の言語や文化と比べて見なければ、アングロサクソンがいかに功利主義に傾斜しているのかよく分からないのです。アングロサクソンの世界だけ見てれば、功利主義の所在もよく見えてこないのだと思います。
論文の書き方みると、すごいわかりますよね。
そうですね。
最初に「ぱーん」って結論書いてあるやつと、なんかこう、あーでもないこーでもないとひねくり回して最後に結論が出てくるやつと。
私は最近アラビア語も少し勉強して、日本語の翻訳によってコーランを全部読んでみました。そこで、アラブ人がどういうふうにものを考えるのか、少し分かった気がしました。というものアラブ人の書いたフランス語の論文は、螺旋状の論理を展開していて、どこに行くのかわからないのです。ところが、コーランを最初から最後まで声を出して読んでみて分かったんですけれども、コーランも同じことが何回も何回も、螺旋状にでてくるんですね。
アラブ人のこのような論理性というのは、コーランの伝統や論理を無意識的であれ、引き継いだものだということが少し分かりました。これはフランス語だけを読んでいてもわからなかったことだと思いました。アラビア語は少し勉強したくらいでは、とうてい歯の立たないむずかしい言語です。それでも、違う言語を学ぶことによって、英語がどれほど特殊であるかがよくわかると思います。
フランス語を例に取ると、フランス語は英語と比べると語彙が非常に少ない言語です。そのため、英語が多くの語彙を使って単純に言える事柄を分析的に語らなければ、相手に伝えることができないのです。言い換えると、フランス語はたいへんに「理屈っぽい」言語なんです。一つの論文にフランス語版と英語版があった場合、両方を読み比べると、英語は非常に単純明快なわけです。ところがフランス語の論文では、ロジックをきちんと分析的に語らないと物事を伝えることが出来ない。ですので、フランスで数学研究が大変に発達してことと、フランス語が分析的に物事を考える言語であることの間に関係があるのかもしれません。
ちょっといまの話聞いていて面白かったんですけれども、僕の学生の頃にフランス語版の『資本論』っていうのが日本語に翻訳されたんです。それをわざわざ日本語に翻訳して、出版されてたんです。それを私の先輩たちが読んで、私は読まなかったんですけれども、すごく分かりやすいと言ってました。ドイツ語の翻訳を読むよりも、フランス語版の翻訳の方がわかりやすいと言ってました。
フランス語経由したほうが分かりやすいということですか。
今のお話聞いてて、なるほどそうなのかと思って。
多分ドイツ語だと複合名詞となって、長くなってる単語を、フランス語では分析的に言い直しているためでしょうか。
今のお話でよくわかりました。なぜフランス語版の『資本論』の日本語訳が読みやすいと言われたのか。さて、少し学生のみなさん向けのお話をさせていただくと、大体中国語というのは先ほどちょっと申しましたように80%ぐらいは英語的に考えられるんですよ。副詞が来て動詞が来る、形容詞が来て名詞が来る。こういう順序というのは英語と同じで基本的に80%ぐらい英語とパラレルに文法事項が理解できるんです。中国語文法を近代語学として最初に説明した人が、アメリカで学んだということもあろうかと思いますが。
だから枠組みを持ってきた。
持ってきたんですね、だから文法書は、品詞分類から入ります。そういったものになってますね。
統語的にそういうふうに決まっているということですか。だから統語が品詞を決めるというか、ここにあったらそれは副詞ですよとか、そういうふうに。
基本的に。
理解できる。
ただ厄介なのは名詞も動詞も同じ形をしている。副詞でも同じ形をしている。だから。
それは文の中の位置では。
位置で大体わかる。
判断するということ。
前に僕ロシア語勉強してるときに、ロシア語というのは順番が、ずいぶん自由で、大丈夫なんだと。
もう格変化すればね、そうそう。
ロシア人が書く英語というのはもう無茶苦茶です。
やっぱりそうなんですか。
もうなんでもいいから言いたいこと言って、そのあとに名詞をおくという、すごい英語。
倒置しちゃったりするんですよね。