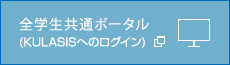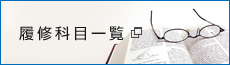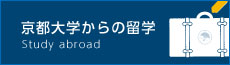第2回 初修外国語担当教員による座談会
そうですよね。だからそれで中国語選んだんだって。私は、これを聞いて、なるほどと思いました。それに、理系の学生さんたちがこれから社会に出て行って、中国人と接しないで暮らしていけるかっていうと、これは出来ない。
最も大きなマーケット。
マーケットですから。これ理系の学生さんでもそうだと思うんです。文系ももちろんそうですけど、これから社会に出て行って中国人あるいはスペイン人フランス人と接触しないことはありえない。そこで、先生おっしゃって頂いたように英語だけで社会人として付き合っていけるかというと、そこでそりゃ1年間学んできれいなマンダリンチャイニーズが話せなくても、でもキーワードがわかったらわかるわけです。それはできると思うんです。そこまでのレベルまでは私は教える自信はあるつもりです。そういうことを考えますと、理系の学生さんが第二外国語を中国語やスペイン語やフランス語を学ぶことというのは社会に出て行った時に実は重要なんだ、と思えます。すいません学問的な話ではなくて。
いやいや、それは重要なこと。
その建築学科の学生たちに学ばされました。そういう考え方があるのかと。
例えばね、この前経済学部の先生に伺った話ですが、経済学部を卒業して企業に行きますね。多くの人たちが例えば商社とかそういうところに。そうすると会社側は大学に何を期待しているかというと、英語は出来て当然。で、会社に入ってきたらすぐ中国語を勉強する必要があると。その時になってから英語を勉強してるようではだめですと。
なるほど。
で、中国語は現場教育しますって言って、要するに英語が使えれば中国に行っても最低限の用事は果たせるだろうと、ぽんと現場に放り込んですぐ仕事をしなさいと言われる様です。中国語は現場で覚えなさいという会社が結構あるというふうに伺いました。
そうそう、だからその。
だからその時点でもう中国語が出来てたら万々歳なんです。
基本出来てないと難しい。やっぱり僕20代後半に入ったら、語学伸びませんから、この時期にやっとかないと、先ほどのお話じゃないですけども、つくづくそう思いますね。
理系の学生にとっても英語以外の言語は重要です。これは、ODAの関連の問題でよく言われることです。西アフリカに日本のODAは多く投入されています。ところが,西アフリカはフランス語の地域が中心です。JICAではどちらかといえばフランス語のできる人達が少ないので、英語圏が中心の東アフリカに日本の援助が偏りがちになるようです。ですので理系の学生で開発援助などに関心があるのならば、大学でフランス語などの初修外国語の基礎をしっかりと勉強することは実用にもつながることだと思います。
そうですね。私がエルサルバドル行った時に向こうで知り合った日本人は、建設会社の人でした。大規模な道路などをつくる公共工事のために駐在員として何年も働いていると。大学は工学系の学部を卒業したとか。その人は行く直前になって慌ててスペイン語を勉強したわけですけども。
必要に迫られて、そうやって現場に放り込まれて覚えるってやり方はあるんだけれども、私が思うのは、その時に本当に何もそれまで勉強しないでいきなり現場で覚えるというのと、きちんと大学で系統的に一回教育を受けていて現場でやるというのでは、その上達度とかその言語に対する理解度とか質がかなり違うんじゃないかと思うんです。先ほども言いましたけれども、国際社会で、言葉が通ずるだけっていう人は沢山います。けれど通ずるだけではなくて、信頼され、リスペクトされるような人になるためにはやっぱりきちんとした教育を受けておくことが非常に大事な感じがしますけど、その点に関しては先生方のご意見はいかがでしょう。
いやその通りだと思います。
そうだと思います。
今の先生のご発言が本当によく納得出来て、今日の話の締めくくりとしてはこれがふさわしいんじゃないかなと思って、今聞いてたんですけれども。確かにそうですよね、リスペクトされるためには英語だけではだめだと。京大卒の学生なんだから、学生たちに社会に出たときに京大卒の看板背負っていくんですから、そういう学生さんたちにとっては、おっしゃるように英語だけで勝負しないでほしいなと思いますね。
荒くれ男達と話が出来ることも大事かもしれないけれども、やはりその国の歴史とか、その言語にまつわる文化とか、色んなことを幅広く知っているということが人間として信頼される基礎になるということですね。
はい、それでは、丁度時間になりました。今日はどうもありがとうございました。


最初に自己紹介、どんな研究されているかなどをお願いします。
私は小倉と申します。全学共通科目の朝鮮語を担当しております。専門は朝鮮半島を中心とした東アジアの思想・広い意味での文化・哲学を研究しています。朝鮮語は文法が日本語と似ていて簡単なので、言語学的な知識を教えるというよりは、むしろ朝鮮半島とはどんなところか、歴史・文化・思想がどういうふうに日本と違っていて、中国と日本と朝鮮半島がどういうふうに違っているかということを、言語の習得の過程で理解していただくのが私の授業です。
研究の方ではどんなことがテーマになのですか?
思想といっても伝統思想です。儒教・仏教・道教ですけれども、私の場合は儒教が主な専門です。朝鮮半島はやはり儒教の影響が強いです。
話がそれてしまうかもしれないけど、新聞で、中国・韓国・日本3カ国の大学の入試問題について書かれていて、それぞれ特色がある。中国では自国の政府の政策意図を答えさせるようなものだが、韓国は、日本、中国との3カ国の比較を考えさせるような問題がでている。私がその問題をみても、中国や韓国がどうなのか知らないような詳細について出題されていました。

韓国はこの15年ぐらいの間、東アジア、世界の中で生きていくということを必死に考えているので、一国史すなわちナショナルヒストリーというものから離れようという気持ちがある。領土問題や歴史認識問題となると、相手の気持ちを考えるというところまでは余裕がないが、少なくとも学問や大学入試のレベルでは関係性の中で考えましょうということになっています。もちろん日本でも3国を意識していた。しかし、朝鮮半島に関する知識を問うことはあまりない、中国についてはたくさんの知識を問われるのですが。韓国にとっては、日本が必ず必要です。アメリカ、中国、日本が重要な国です。
大学入試は、私は54歳ですが、それぐらいの年齢の韓国の人は、受験勉強の時に京大や東大の数学の入試問題を解いていた。韓国の昔の受験参考書は日本の真似をしていたんです。数学などは特に国に関係ありませんから。
数学の関係で韓国にも行ったことがあるが、一番驚いたのは韓国の学生は先生とすれ違う時は必ず立ち止まってお辞儀をするという、日本の学生では考えられないことがあります。
それは「儒教」ですよね、数学やってる人も、物理やってる人も儒教ですから。
なるほど、それが儒教ですか。
逆にいうとアカデミズムの世界ではそういうのが残っているとよくないという反省も韓国ではよくあります。自分より職階の上の人には到底逆らうことができない、命令に従わなくてはいけないというのがまだアカデミズムの世界でも残っています。
確かに、日本はそういう感じではないかもしれませんね。