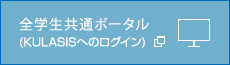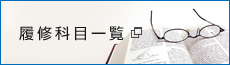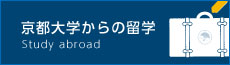第2回 初修外国語担当教員による座談会

中国語は順番通り書いてもらわないと分かりません。やっぱりそれ動詞プラス目的語で、動詞の位置は決まって参ります。でも大体80%ぐらい英語とパラレルに考えることが出来て、残り10%は、あ、こういう言い方は日本語でもするなと思って、日本語的な発想で理解できる。これやっぱり日本語が中国語に影響を受けてるからです。残りの10%が中国語独特のもので、これをマスターするのに前期で1回、後期で1回ぐらい山がございます。この山を乗り越えて貰いたいと学生のみなさんによく言うんですけれども。で漢字ももちろん異なりますけれども、例えば京都大学ってこれ全く同じ漢字です。違う漢字ももちろんございますが、北京と書いたら北京です。中華人民共和国、「華」という字が違いますけど、中華人民共和国の「華」以外は日本の漢字と同じ、そういうおまけに中国人は大体19世紀の末ぐらいから日本語を通して西洋文明を学ぶようになるんですね。昔は逆だったんです。それ以前は、日本人は中国語を通して西洋文明を学んでたんです。「万国公法」(国際法)という言葉がございますが、万国公法というのは日本人は実はオランダ語で学んでたんじゃない。中国語に翻訳された、英語から中国語に翻訳された中国語を読んだんです。当時の人たちも、中国語を読んだんです。読めたんです。でも日清戦争に負けた辺りから、中国人は日本に留学して参ります。
それから、日本語を通して西洋文明を学ぶんです。ですから政治、経済、社会、こういった言葉は全部日本人が作った言葉でございまして、「哲学」という言葉は西周が作ったし、「演説」という言葉は福澤諭吉が作っ。こういったふうに日本人が作った言葉がいっぱいあります。それが定着している。我が京都大学の学部名の文学・法学・経済学・教育学・工学・医学・薬学、全部が中国で漢字として通じます。ただ、2つ通じません、理学とそれから総合人間学。
それは日本語でも総合人間科学部はね。ちょっと説明がいりますから。
理学は何になるの。
理学は実は中国で哲学の意味なんです。もともと中国に理学という言葉が別にある。朱子学で使う言葉でした。
なるほど。
じゃあ日本語で言う理学は中国語だとなんて表現されるんですか。
中国ではそれが物理学部とか、化学学部、地質学部、とか。
それはアメリカの大学でも理学部という学部はないんですよ。数学は工学に入ってるところが多いですし。MITなんかもそうですし。
中国語のことに戻りますが、発音がいささか厄介です。けれども、学生のみなさんに言うんですけれども、今から僕の顔を見て僕の口元を見て僕がこういう口をするからこういう口をしなさいって。舌を思いっきり曲げて、舌を前に出してとか、こんな言い方をするんですが、恥ずかしがらずにそれは中国語を発音しているときには口の形が色々動くから変な気がするかもしれないけれど、それを恥ずかしがらずにって。どういうふうに舌や唇を動かしたらどういう発音が出来るかというのは自分たちが勉強したことを学生に伝えるようにしておりますから、そういった点では、中国語の発音は、マスターできないものではありません。
私どものやっている授業の、第一学年の授業はほとんどコンピューターを使った授業をしておりまして、コンピューターでボタンをクリックすればそこで音声が流れてそこで発音記号が出て、それでそれを音声を聞いてもらう。で同時に教科書も作っています。市販の教科書に比べ、内容はより豊富です。特に理系の学生の皆さんは1年しか勉強しませんので、1年でも大丈夫なようにかなりの基礎としてはかなり進んだことまで教えます。こうしたレベルの中国語をコンピューターを利用して学びます。コンピューター教材をウェブ上にアップしております。これ、スペイン語もそうですか。
いやスペイン語はね、再履修者コースだけです。
中国語は、自宅でもどこでも勉強出来るようにしております。それこそ京都大学の教育理念である自学自習というのを地で行っている教育体系ではないかと思います。2年生になったら会話重視とか文法重視とかそれから読解重視とかいったクラスを沢山作って、ニーズに答えられるようなカリキュラムを作っております。
西山先生がおっしゃったように、異なる言語による異なるロジックが存在するというのは、まったくその通りだと思うんですよね。勉強については「かじる」という言い方はあんまりいいイメージで使われないことが多いですが、「かじる」というのは非常に重要だと思います。「かじる」ことで自分の中に地図ができます。ある概念や考え方は、別の概念や考え方とどういう関係にあって、どういう時には役に立ち、どういう時に役立たないか、といったようなおおまかな地図が頭の中にできていく。
親和性がグッと増しますよ。

そうですね、だからそういう意味で、英語だけなく、その他の言語も学ぶことは非常に重要だと思います。一方で言語というのは身体訓練を要求するものなので、その部分はちょっと大変なんですよ。言語学習については、よく水泳の話を引き合いに出します。泳ぎ方をいくら座学で聞いたって泳げるようになりません。実際に泳いでみなければ泳げるようにはならない。また、座学の意味も実際に体を動かすことで、「ああ、あの説明はこういうことか」って体に入って理解できてくるんですよ。だから「とにかくやってみる」ということは言語学習において非常に重要です。新入生にはまずそのことをアドバイスしたい。ただ、「とにかくやってみる」というやり方はおそらく言語によって全然違う。特性が違うからです。先ほど江田先生がおっしゃったように、スペイン語の音は簡単なんです。簡単というのはちょっと語弊がありますけど、日本語話者にとっては発音しやすいほうだと思います。2コマ3時間あれば、読むだけ発音するだけはできますから。文字はこれだけあって、音とはこう対応していますよ、この組み合わせだとこう読みますよ、というのをやると、2週の授業でちゃんと読めるようになっちゃいます。
2コマ、2週どっち。
90分が2回。だから意味は全然分からないんですけど、スペイン語の記事を音読はできるようになります。そういうとっつきやすさはあるんです。ただそこからは、それこそ日本語にはない冠詞だとか、先の方に行くと接続法だとか、まず概念を理解するのにちょっと骨が折れるものもあります。先ほどの中国語の10%にあたるようなもの、日本語や英語の類推ではつかめないというものはあって、でもそこが逆に言うと面白い。全然違う体系なんだっていうことがよくわかるポイントなので当然難しいんですが、そこをやることが、先ほど言った脳内マップみたいなものを作る上で非常に役に立つわけです。
折角こういう場ですのでちょっとお二人に質問させていただいてよろしいですか。先生方1年生に、その外国語フランス語スペイン語を教える時に暗唱させますか。暗唱、テキストの。