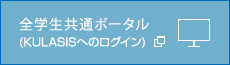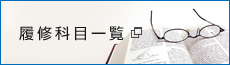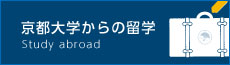第2回 初修外国語担当教員による座談会
今、おいでいただいているのはフランス語、中国語、スペイン語です。この3つは履修者の数が多い言語ですね。学生のことはちょっと後にして、みなさんご自身でフランス語ならフランス語について、どんな特徴、面白さ、魅力があるか、語っていただきましょう。

フランス語が世界の広い地域で使われていることは歴史と深い関係があります。特にフランスは17世紀から世界中で植民地を作ってきたことを思い起こす必要があります。私は植民地でのフランス語の問題に大変に非常に関心を持っていす。 日本は幸いなことに植民地にされたことのない数少ない国ですので、支配されるという経験がありません。そのために、外国語、特に英語に対する憧れが抜き難くあるのだと思います。ところが、フランス語は世界各地を支配してきた言語なのです。日本は戦前に朝鮮半島や台湾を支配した経験がありましたが、戦争で負けたために植民地を放棄しました。
そこで、独立以降、日本語はそれらの地域では使われることはなかったのですが、フランス語の場合はアフリカやアラブ世界では独立後もほぼ公用語に近い形で残っているところが多いわけですね。つまり、アフリカ人であれ、アラブ人であれ自分達を支配した人間の言葉を使わざるを得ないのです。アルジェリア人の中には、フランス語を戦利品であると称する人もいます。
また、別のアフリカ人は、フランス語を植民地という廃墟の中から舞い上がったフェニックス(不死鳥)だと言っている人もいます。いずれにしても支配者の言葉を使わざるを得ないということは、人間にとって非常に複雑な感情を招くものだと思います。日本人はこのように支配された経験がないために、複雑な言語感情が生まれにくいのだと思います。フランス人がフランス語を使っている限り、とくに複雑な言語感情は発生しないでしょう。むしろフランス語は立派な素晴らしい言語だ思うかもしれません。しかし、フランス人以外の人間がフランス語を使う時には、歴史の重みがそこに隠されているのだと思っています。

中国語がどのような言語なのかと申しますと、私、大学の一年生の時にこちらで中国語を学んだときに先生が教えてくださったんですね、中国語には3つの文法しかないから、安心しろ、と。主語が来て述語が来る、修飾語が来て被修飾語が来る、動詞が来て目的語が来る。この3つだけしか文法はないんだ、この3つは実は英語と同じなんだ、君たちは簡単に学べるんだ。そうやって励ましてくださった。もうひとつこの先生の教えてくださったことは語学には能力というのは関係ないんだ。誰にでも出来るんだ、ただし時間の早い遅いがある。そういうふうにおっしゃってくださった。で、そういうことを考えますと、中国語というのを、例えば人称変化がありません。それから格変化がありません。冠詞がありません。それから時制がありません。
例えば、今喋ってる言葉がこれが過去の話なのか、現在の話かっていうのは、そこに例えば今日という言葉が書いてあったらこれは今日の話で、でなにかヒントがないと過去の話かどうかが区別出来ないケースがある。そういう人称変化、時制、格変化がないというのは中国語の大きな特徴だと思います。日本語とも違いまして、動詞の変化もございません。それ以外で何を以て中国語は勝負してくるのかっていうと、やたら語彙が多いんですね。で漢字がやたら多い。日本で最大の漢和辞典というのは13巻もあります。そういう語彙でもって勝負するというところと、それからそれぞれの単語に高低アクセントがある。欧米言語の強弱アクセントでなくて。日本語でも、この高低アクセントがあります。関西人の発音でもこうやってアクセントが上下しておりますけれども、こういう高低アクセントが4種類ないし5種類あって、それから発音が日本人に出来ないようなものがあります。スペイン語は確か日本人に出来ないような発音が殆どないと聞きました。
ないと思いますよ、みんなできますよ、学生は。
中国語は、母音も子音も、日本語にない発音があって、やや難しい。それから単語を沢山覚えなくちゃいけない。しかもそれを音声として覚えなくちゃいけないというのが中国語の少し厄介なところかな、と思います。文法的には難しくありませんから。自分の興味のある歴史の文章だったら1年生のころに読めました。読む気になったら。それこそ返り点を打って読むんです。そういう意味では中国語っていうのは日本人にとって学習しやすい、しかしこれは私共の同僚の阿辻先生という方おっしゃっているですけれども、この先生は一年生のときに、フランス語を勉強してらっしゃった。でフランス語1年間勉強したらフランス語というのは坂を登っていて、到達できるような言語なんだっておっしゃっておられました。ところが中国語というのはこの坂がだらだら坂で、だからずっと登っていくようなところがあります。あともう一つ申し上げたいのは、只今フランス語の公用語は全部で46カ国とおっしゃってましたね。
それぐらいですね。
前に塚原先生に確かスペイン語の公用語は十幾つかとお聞きしました。
21ですかね。
こういうことを言われると中国語としては立場がない。我が中国語というのは公用語になっている国は、中華人民共和国とシンガポールしかございません。あと「国」ではなく台湾と香港がありますが。
地域とかっていう言い方をする。
だから「地域」を入れても4つしかございません。ただし話者の数は、たいへん多いのです。13億人ございますから、こちらの方ではスペイン語フランス語に負けないと思います。
それから各地にあるそのコミュニティーがすごいですよね。
ただコミュニティーは世界各地に沢山あるんですけど、そのコミュニティー、例えば僕シンガポールのチャイナタウンにいって買い物しようと思ったら言葉が通じないんです。
中国語が通じない。
それは北京語ではない。マンダリンじゃない。広東の潮州というところの言葉なんです。それが通じない。
京大ではどこの言葉を教えるのですか。
私どもは北京語しか教えません。私たちは、広東語はわかりませんし、上海語もわかりませんし、四川語もわかりませんし、それからそれ以外の各方言、大体5つの方言地域がございまして、それぞれがまたいくつもの方言に分かれています。まあ簡単に言ってみれば青森言葉、鹿児島の言葉、あるいは、沖縄の言葉、こうした差以上にあるかもしれません。
だからこれ方言って今おっしゃってますけど、それヨーロッパ的に言えばもう別の言語ぐらい違うわけですよ。ただ文字で結びついてるから。
中国でも、書いたものはもちろん共通で分かります。広東語の口語では、音声が違うから別の漢字を使うんですが。
台湾。
台湾は半分より少ないぐらいが北京語を話して、半分より多めが福建の言葉で、普通台湾語と言われます。
それはかなり違うんですか。