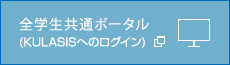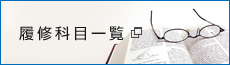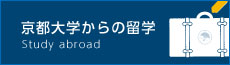第2回 初修外国語担当教員による座談会
かなり違います。例えばそうですね、例えば「もしもし」というのは北京語ではウェイと言うんですけども、広東語ではワイって言います。でみなさんちょっとどいてくださいっていう時に、ワイワイワイって言います。バスを降りるときに向こうのおばさんはワイワイワイワイワイって言いながら降りていくんです。全然言葉が違ってきております。ただし、今では、かなり北京語が通じるようになっています。私が30年ぐらい前留学しているときは、普通の人はそれほど北京語が上手でなく、日常は、それぞれの方言を話していました。
バスから降りてきたワイワイっていうのは、その北京語と台湾語で漢字は同じ字なんですか。
漢字は同じですね。読み方が違います。例えばそうですね、それから北京語で、「はい」っていうのは「シー」って発音するんでしがが、広東語ではこれはどういう訳か、「ハイ」って言います。例えば香港の歴史映画なんか見てまして、皇帝が部下になにか命じますと、その部下が「ハイ」って言って頭を下げる。なんかそういうところを見ると楽しい言語なんですけれども。ただ先ほど申しましたように、現在は随分北京語が普及しておりますので、北京語で日常的に生活が難しいということはないと思います。但しそれでも中国のテレビで、一般市民のインタビューが映りますと、必ず字幕がつくんですよ。分からないからですよ。日本で字幕なんかが出ないケースでも必ず付きます。
でも事実的にはみんな割とバイリンガルだっていうような感じだと思えばいいんですよね、多分。
自分のところの方言と、それからマンダリンとを話せる。私は、南京大学というところにおったんですけど、南京そのものは北京語系統の地域なんですけれども、でもやっぱりかなりちがう。中には先生の中に方言でしか授業出来ない先生がいて。
京大でも関西弁でしか授業しない先生もいる。
それを 言われると、私もそうですが・・・。でも、テレビなどでは関西弁は結構全国区だと思うんですけれども。いまの事例ですが、もっと小さな地域でしかわからない言語でもって南京大学で先生が授業をしていて、あの先生の授業は全然分からないと、中国人の友人が言っておりました。
あと、私は南京大学に学んでいたとき、蘇州というところから出身の学生と一緒に住んでたんです。そういう外国人留学生に対する配慮を当時の中国政府はしてくれたものです。で、留学生宿舎というのは広くて、普通の学生宿舎より恵まれてるものですから、ぼくと一緒に住んでる中国人の蘇州人の友達が集まってくるんです。だから例えば南京大学だけれども蘇州人のグループがあって、同じ言葉を。
同郷会みたいな。
同郷会みたいな感じ、集まってくる。で彼らが私の部屋で4人5人もおしゃべりするんです。さっぱりわからない。おしゃべりしてもさっぱりわからない。だからお前たち頼むから「中国語」で喋ってくれって言ってたんですけど。ですが、彼らにとってそれは「中国語」ですから喋り続けるんですよ。ところが、面白いなと思ったのは突然北京語で話し始めたんですよ、彼らが。で何を話し始めたかというとそこで学校の授業についてなになに先生の歴史哲学は云々かんぬんという話になったんです。つまり学問的な話というのは学術用語というのは北京語しかできないんです。スーッと変わって来ました。全く自然に、あれは興味深い事だなあと思って。よく紹介するんですけど。
用語の部分だけを、マンダリンでしゃべるんじゃなくて、話全体がマンダリンになっちゃうわけですか。
そうです。何も彼らは、「これからマンダリンで話すぞ」と宣言した訳ではないんです。
そうやってその言葉で大学で勉強してるからなんですね。
そうですね。それを蘇州語では話さない。あれはとても面白かったですね。
スペイン語ではどうですか?
そうですね。江田先生がお話になったようなことは、社会言語学という学問分野で扱うコードスイッチングや言語接触という話ですね。
そうなんですか。

私や西山先生はそういうところにも足をかけていますが、その観点からしても興味深い話です。スペイン語の中でも同じようなことがあります。数え方にもよりますが、スペイン語の母語話者数は4億を越えると言われています。その9割ほどは広大なラテンアメリカに広がっており、スペイン語自体が非常な多様性を持っています。
また、先ほど話したように、スペインの中でもスペイン語以外の言語が話されている地域があり、スペインの人口の4割程度は多言語地域に住んでいることになります。ラテンアメリカでも先住民の言語が残っている多言語地域があります。ペルーなどで話されているケチュア語や、パラグアイやアルゼンチンなどで話されているグアラニー語などがその例です。そういう地域では多くの人が多言語話者です。スペイン語も通じるけれどもそれ以外の言語を家庭や親しい友人の間で話しているという、今、江田先生もおっしゃったような話があります。スペイン語の多様性の話に戻ると、例えば「あなた」に該当するtu(二人称単数)という人称がありますが、アルゼンチンなど、tu(トゥ)に代えてvos(ボス)という人称が使われている地域があります。
それは現地の言葉から来てるんですか?
いえ、現地の言葉ではありません。スペイン語の古い形で、遡ればラテン語です。
トゥがボスになるんですか。
アルゼンチンなどではそのようですね。tuとvosの両方使うところもあるんですが。vosに対応する動詞の活用もtuとは違うんです。ですから、アルゼンチン映画なんかみると最初よくわからなくてですね、一本見終わる頃にようやく慣れて分かるようになるとか。また、語彙も豊かなので、たとえば「バス」を示す単語も、スペインだったらautobusですが、メキシコではcamionと言ったり。発音でも、スペインではceというつづりを[θe]と発音するところが多いですが、ラテンアメリカでは一般に[se]と発音します。私はコスタリカに一度行ったことがあるんですが、スーパーで買い物をしたあとに、レジを担当していた18歳ぐらいの女の子になにか言われたんですよ。ところが何を言われたのかわからない。それで聞き返したんですよ。同じことを言われたけれど、やっぱりわからない。そこでもう一回聞き返したらだまって手を振って「もういいから、行け」みたいな。手で追い払われたんです。
私にも、聞き取れないことはよくあります。
相手がスペイン語の若者言葉を使ったのかもしれませんが、たぶん、私の知らないスペイン語のバリエーションを話していたんだろうと思います。自分はスペイン語を勉強してきたつもりだけど、知ってるスペイン語はわずかなスペイン語だったなっていうことがよくわかりました。私はスペインで勉強したので、ラテンアメリカのスペイン語というのはあまり知りません。スペイン語の教員をやってますが、知ってるスペイン語というのはごく一部にすぎない。