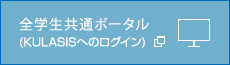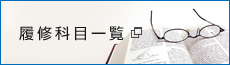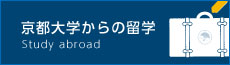第2回 初修外国語担当教員による座談会
そのやっぱり先生が教えてらっしゃるスペイン語というのはマドリードを中心とする地域なんですか?
マドリードというかスペインのスペイン語ですね。
全域でやってる。
スペインでも南のアンダルシアの方に行くとまたちょっと違うんですよ。
バスクって全然違うんでしょ。
バスクにはバスク語っていうのがありますから。
バスク語というのはスペイン語なんですか。
いや全然違うんです。バスク語は非常に古い言語だと言われています。なんにせよ、スペイン語というのはいろいろなものへのアクセスを提供してくれるものだと言えます。特にラテンアメリカへアクセスする場合は非常に面白いし、不可欠でしょうね。もちろん、他の言語もそれぞれが特有のアクセスをもたらしてくれるのですが。ちなみに、ブラジルというのはポルトガル語ですけども、公教育ではスペイン語教育を行っており、言語的な近さもあって、かなり「通じる」らしいです。
ポルトガルでスペイン語が通じるということですか。
今のはブラジルの話ですが、ポルトガル語話者でスペイン語が分かる人は多いでしょうね。
京大に赴任する前は愛知県でラテンアメリカ系の子どもの学習支援活動に関わっていました。ペルー人とのつきあいが多かったのですが、ブラジル人ともつきあいがありました。わたしはスペイン語、相手はポルトガル語で話しているのですが、身振り手振りも交えて、コミュニケーションはなんとか成立していました。例えば冠詞の形とか、前置詞の形など、単音節でよく使われる単語を覚えておくと、だんだんわかってくる感じです。音がちょっと違うとかありますけどね。だからそういう意味ではラテン系言語は潰しがきく。ヨーロッパへ行くと「スペイン語もイタリア語もフランス語も話せる」という多言語話者は珍しくありませんが、日本語を話している身からすると、そりゃちょっとズルいだろって言いたくなる感はありますよね。
近年、ヨーロッパで研究の進んでいる分野に,隣接言語の相互理解教育というのがあります。これは、例えばフランス人がイタリア語やスペイン語を読めるようにしたい、ただ文献を読めるようにするための教授法の開発です。読むことに特化した教授法はさまざまな開発が進んでいます。およそフランス人がスペイン語を読めるようには、50時間で良いといわれています。
本当それぐらいだと思います。
ですから、フランス人が俺はスペイン語できるといっても、あまりたいしたことではないのです。

語学教育っていうのは、ヨーロッパでも、非常に重要なこととして、数世紀前から、かなりいろんなインテリが言っていてね、で例えば経済学者のジョンスチュアートミルなんかは大学改革の本の中で語学教育のことをもう100年ぐらい前に言ってるわけですよ。
ヨーロッパ人として、多言語を勉強するためには自国語の次にラテン語を勉強するのが非常に近道だというようなことを言ってるわけですけど、それは私からみたらラテン語というのは文法というのは恐ろしく複雑でよく分からないんですけれどもね、語尾が。
格変化がすごいですからね。
だけどもヨーロッパ言語を勉強した人にとってはそれが身につくとそれをもとにみんないくつもの言語が分かれていったからということで非常に理解しやすいということなんだと思います。それで正しい理解ですか。
例えば学者語と言われるような難しい言語というのは、ラテン語かギリシャ語を基礎としています。ですから、ラテン語かギリシャ語が分かれば、ほとんどの学者語は分かるわけですよね。
アメリカ合衆国に留学した時に、読む英語論文の専門性が高くなればなるほどどんどんわかるようになるという話を、メキシコ人の学生から聞いたことがあります。
そうですよね。
要するに、ラテン語起源だったりギリシャ語起源だったりする学者語部分がみんな同じなんです。
それは先ほど僕が1年生の時に専門論文読めたのと同じということですね。